| 今週は主人が出張でいなかったので、秋の夜長というより明け方までかけて、 やっと父兄に長いこと借りていて、見られなかったDVD「北京ヴァイオリン」を見た。 やっと父兄に長いこと借りていて、見られなかったDVD「北京ヴァイオリン」を見た。
マンガ,本といい、私は本当に生徒のお母さんによって、充実した余暇を過ごさせていただいている。
元はと言えば、私は根が単純で、好奇心が強く、人の薦めてくれるものを素直に受け取るたちだから、こうして忙しくとも有意義な毎日が送られるのかもしれない。
本当に皆さんに感謝である。
これからも良いと思うものは"食べ物"でもなんでも紹介していただきたい。
"冬のソナタ"も"美味しいランチ"も"本"も"マンガ"もすべて父兄の皆様のお薦めだから、これが、私が唯一"ピアノばか"にならずに毎日を過ごせる由縁です!
さて「北京ヴァイオリン」だが、時は現代、田舎の貧しい天才少年がヴァイオリンを背負って、父親と北京の大都会に立身出世を目的に出てくる話である。
さぞかし、音楽教育映画と思い、ワクワクしていたが、ちょっと違うのだ。
父親が、大して厳しくない上、そのズッコケさもさることながら、ヴァイオリンを弾かせたら天才という少年が、ちょっといかがわしいが心の優しい若い女の子(日本だとヤンキーというタイプ?)に憧れ、その周辺をうろちょろするあたりは、首をひねりたくなる。
北京に来て最初についた先生は、何と野良猫を何匹も抱えて、家の中はスラム化してほとんど浮浪者風で、ちっともヴァイオリンを教えない。父親は、なけなしの全財産を、自分がかぶる帽子の中に隠し、息子の才能を開花させようと必死でレッスン代を稼いでいるというのにだ。
しかしこの教師時々ドキッとしたことを言うのだ。
「ヴァイオリンで成功する人とヴァイオリンがうまい人とは違う!」フーム、何か分かるような気がする。
一見人生の落伍者の様に見えるこの芸術家タイプの先生は、不器用な世渡り術で、音楽の心をつかみつつも、人生の成功者ではない訳である。
少年は、ヤンキーの彼女のご機嫌取りみたいな事をしながら、その感受性を発揮しながら、北京の底辺の貧しい人たちや、自分の先生を興味深く観察し ているところが面白い。 ているところが面白い。
そしてついにその父親が、国際コンクールを指導する今をときめく教師を見つけた時には、少年はその彼女に何十万もの、コートをプレゼントする為に、自分のヴァイオリンを売ってしまうのだ。
それを知った時の父親の怒り、「もっと怒って!」画面に食い下がるくらいであった。
子供というものは、自分の持っている才能というものを理解していない。
父親とけんかして、当てつけのようにヴァイオリンを売ってしまうが、それがどんな事なのか全く分かっていない。映画なのに腹が立った。
紆余曲折あり、結局北京の大先生の下でライバルである少女と、国際コンクールの出場権をめぐって住み込み合宿が始まるのだが...。
貧しい父親を、教師は退け、少年の才能を自分のものにしようとする。出世の為に自分の才能を利用されていることに気づいた少年が、コンクールの出場権利を直前でかなぐり捨て、田舎に帰る父親のところへ走る。
父親に追いついた駅の構内で、コンクールで弾くはずだったチャイコフスキーのヴァイオリン・コンチェルトを弾くという姿がクライマックスだ。
「僕の音楽は父さんと共にあった!」「父さんあっての僕だった!」「父さん無しで僕のヴァイオリンは鳴らない!」、と画面から聞こえてくるようで胸を打たれた。回りで聴いているのは貧しいがハートを持った底辺に働く人々だった。
これが母親だったら、さしずめマザコンで映画にはならないのだろう。
この映画は、音楽というものが何の為にあるかを問いかけていた。
少年の才能という花は、父親の愛という植木鉢の下でこそ、咲いていた。少年がそのことに気づいたという事だ。
それを裏付けるシーンに、大先生がライバルの少女がミスなく完璧に弾く姿を見て、「ダメだ!君の音楽には心がない!」「空の銃が人を撃てないように、心のない音楽は人の心を打たないものだ!」「私は、技術を教える事が出来ても、心を教えることは出来ないのだよ!」「心は自分で磨くものだ!」というところに、あまりに同感してしまった。
今の子のように、忙しい子に"心を教える"事は難しいことだ。
この心の持ち方というものは、友人と遊んだり、親兄弟や回りの人との確執や、色々な体験から学ぶことが事だから、ヴァイオリンだけ与えられ、ぬくぬくと幸せに何不自由なく育っている子に、「心を磨け!」と言っても、そうそうに磨かれるものではないのが、現実なのだが。
そのことはさておき、音楽は、要は"ハート"だということだ。
人への思いやり、暖かい真心、それらはどんな技術をもっても埋められる事が出来ない。
人としての暖かさこそ、音楽が必要としているものだと問いかけていた。 |
|
|
|
| 最近は、夏にはまっていた「冬のソナタ」のDVDを再び見ている。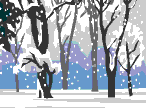
DVD BOXを買ったとはいうものの、ほとんどチェック出来ず、毎日仕事に追われていたので、最近になって、また自分の中でリバイバルだ!見終わったら、また韓国版を見るつもりだ。
韓国ドラマに、はまった友人達は、次々と新しいドラマを見ているというのに、私はゆっくり時間がとれないのでこんな形で停滞しているが、しかし、根がしつこいたちなので(高価なポラリスネックレスも買ったことだし?)ずっとこの世界にいることにした。
なので、最近はまた韓国食にもはまり、大久保に東京のお母さん達と一緒に出かけ、韓国食材を買ったりして、みそチゲばかり食べている。
日記だが、今週は「源氏物語」を読んで、エッセイにまとめて書いてみたので、ぜひ覗いてみてください! |
|
|
|
| 今週は暇さえあれば、漫画を読んでいた。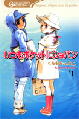
と聞くと、皆さん先生の知性と教養、年齢を疑う方もいるやもしれないので説明を加えると、何故か先週から手元に漫画本がいっぱい届き、生徒の親御さん数人から同時に「また感想を聞かせて下さい!」と言われてしまった手前、ひたすら読み耽ったという訳である。
子供の頃は絵が大好きで、漫画家になりたいと真剣に考えた時期もあった。
中学に入り、親友の漫画がうまいのをみて挫折した(彼女は美大に行ったが...。)
油絵画家は母にルノワールと比較され、「あなたは絵では身を立てられない。」と断念させられ、その当時一番嫌いだった(練習もだが、人に指図されるのが何より大嫌いだったのだ。)ピアノの道に進む皮肉な人生を選ぶ羽目になった。
漫画も母がうるさいので、隠れて読んだ。見つかると、即廃棄処分である。
ひとつ年上の双子の姉達と、ケンカすると母に漫画を読んでいることを告げ口されこっぴどく説教をくらったものであるから、漫画⇒罪悪であった。
母の言によれば、何故あんなに細かいコマを追えるのか?気が知れないという訳である
私からすれば、主人公は元より、衣装や家具などを絵で追っていた気さえするから、今でも自分の趣味に、ベルバラが入るのもそのせいやもしれない。
花,ガラス,シャンデリア,レースにめちゃめちゃ弱い体質だが。(最近は年齢と共に、また時間が無く掃除が出来ないのでずいぶんすっきりした好みになったが)
そんなわけで、子供のころは漫画が大好きだった。
年をとるにつれ、何故か活字が好きになっていた。今では漫画はコマを追うのがしんどいくらいである。
また活字の方が、イメージが膨らみ、楽しいから、絵で答えの出ている漫画はつまらないし、おっくうに感じて、何十年も読んでなかったのだが。
最近の若いお母様達は、漫画も文庫本感覚で読んでいる。
「とても面白いから、先生是非読んで」と借りたのが"ポケットにはいつもショパン"それと"神童"、そして源氏物語を描いた"あさきゆめみし"である。
"ポケットにはショパン"は2巻、"神童"は4巻"あさきゆめみし"は7巻あった。
もうこうなると喜べない。最初は早く返さねばと読んでいた。漫画の読み方を忘れていたので、最初はコマを追うのと吹き出しを読むのに、一苦労なのだが、次第に慣れていったらこれが面白い。
もともと好奇心も強いし、頭は悪いけど、めちゃめちゃ柔らかい体質だから、あっという間に"ショパン"と"神童"は読破した。
この2つの本は、音楽学校に通うピアニスト志望の子供達の物語だから、知っている事も多く、興味深かった。
何しろ音楽の世界は、特殊だから、(結構、根性物である。)題材にする方もかなりの予備知識を持って臨まないと、書けないだろうから、中々鋭いところを突いていて面白かった。
特に"神童"は、手塚治文化賞優秀賞、文化庁芸術家優秀賞など数々の賞まで受賞している上、新聞にも紹介されるほどの作品で、最後の場面が特に感動的であった。
親との確執,ピアノの練習のつらさ,ライバル出現,コンクール出場,音楽学校での友人や先生との葛藤,留学そして挫折,ついには真の音楽の意味に目覚めていった主人公達を描いて、リアルでかつ身につまされる場面が数多くあった。最後にホロッときて、いい年して漫画に涙するなんてと我ながら気恥ずかしかったが、本当に内容は素晴らしいと思う。
"あさきゆめみし"はご存知紫式部原作の古典"源氏物語"の漫画本である。
これがまた大変、漫画といえど細かい上、史実に忠実。一冊読むのにヒーヒー言っ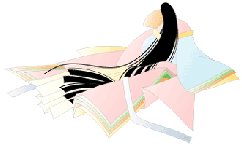 ていたが、源氏物語は本で読むのは大変だから、"あさきゆめみし"を読むようにと、かの慶応女子高校他でも古文の先生のお墨付きだと聞き、それならと一念発起して真剣に読み出した。 ていたが、源氏物語は本で読むのは大変だから、"あさきゆめみし"を読むようにと、かの慶応女子高校他でも古文の先生のお墨付きだと聞き、それならと一念発起して真剣に読み出した。
いづれの御時にか、
女御、更衣あまたさぶらひ給ひける中に、
いとやむごとなき際にはあらぬが、
すぐれて時めき給ふありけり。
と昔暗記までした光源氏がよみがえった。
"源氏物語"については書きたい事が山ほどあるので続きはエッセイで詳しく書きたいと思います。 |
|
|
|
| 10月31日横浜みなとみらいホールで日本アンサンブル・コンク ール受賞演奏会が開かれた。 ール受賞演奏会が開かれた。
うちの教室の卒業生の生徒姉妹が、このコンクールの2台ピアノデュオ部門で最高位の最優秀賞、全音楽譜出版社賞をとったので、これに参加していたのだが、私は東京のレッスンが休めなかったので行かれなかった。後で無事に演奏出来たとの報告を受け、ほっとした。
藤枝に主人の転勤で付いてきて、ピアノ教室を始め、最初の生徒は、既にピアノの先生として独立し、私の教室も手伝ってくれているが、この姉妹は、私の30代の猪突猛進でピアノまっしぐらの時代に育った生徒達である。
故福田靖子先生と共に、ピティナの代表としてザルツブルクで演奏旅行に参加したり、ポーランドのワルシャワにコンチェルトの演奏旅行にも参加したりした。
そして、仙台での若い芽のチャイコフスキー国際コンクールに姉妹揃って合格し、仙台で過ごした事等々、数々の思い出と共に私のピアノ教師人生に花を添えてくれた2人だった。
小さい時から、お嬢様道まっしぐらで、何の不自由もなく育った2人も、受験の時には家庭内の事情などで苦労してしまった。そのせいか思春期の姉妹げんかも凄まじかったのだが、大学生になって二人して東京で生活するようになったら、気味悪い程仲がよい。
2人でレッスンに来る時も、いつも「よろしくお願いします!」と相手に対してお互い声を掛け合い、2台のピアノに向かう。
もちろん私に対してもいつも事細かにいろいろな報告をしてくれる。
天然だったお姉ちゃんはその優しさに加え、回りに対する細やかな心遣いにいっそう磨きがかかった気がする。多分、独り暮らしで成長したのだろう。
独創的で自由闊達な妹のピアノに対し、いつも控えめでありながら主張しつつ、しっかり合わせていく。
2人のデュオがぴったりなのは、姉妹であることに加え、共通の音楽性がある事に他ならないと思うが、その成長の手伝いをしてきた事、そして今後も成長を見守り続けていく事が出来る事を嬉しく思っている。
私も本人達も、いつか2人がデュオのプロとして、デビューすることを夢見ているのだが。
プロデビューといえば大変びっくりしたことがもう一つ。うちの教室の小5のYちゃんが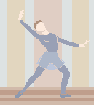 、超難関のサンミュージックのオーディションに受かってしまったのだ。 、超難関のサンミュージックのオーディションに受かってしまったのだ。
サンミュージックといえば、あの松田聖子、古くは桜田淳子などの生みの親、相澤社長率いるタレント養成の音楽事務所である。
オーディションもピアノの比では無く、1,500人中たった3人しか合格できない難関中の難関の中で、更に子供はたった一人だったというから、すごい倍率をかいくぐったとしか言いようがない。
しかも、ダンスや歌の試験など、4次試験まであったというのだからすごい。
歌もダンスもアピールしながら、体中で歌い踊る姿をビデオで見た事があるが、"プロ顔負けだ"と思いびっくりした。
これからは、週一度東京四谷で本格レッスンを受けるというのだが、レッスン代も無料、交通費も出るというから、タレント"金の卵"扱いではないか?だからといってタレントになることを保証されたわけでもないのだろうが。夢を見るという意味では限りなく正夢に近い夢ではないだろうか?
ピアノ以上に才能の世界なのだろうが、いつも感心していたのはご両親の子供への接し方だった。
いつも精いっぱい笑顔で子供を信じ、応援して止まない。私がブルグミュラーの見本を弾いても、ご両親揃って「何と素晴らしい」「まるでCDみたい」と後ろから二人してパチパチと拍手されてしまい、戸惑ったことがある。
たかがブルグミュラーの見本を間違えなく弾いただけで、こんなに感動されるのだから多分子供に対しても、日頃から褒めて、褒めて、"素晴らしい"の連発なのだろう。
ちょっとくらい、歌がうまいからといっても、我々は手放しで褒められないから、結構冷めているのか、どこかで子供の才能の芽を摘んでしまっているのかもしれない。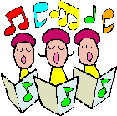
小さい頃に人と違った才能を見せたら、とにかく褒めて育てて、やる気を伸ばし、人前で照れず、堂々と歌ったり、踊ったり出来る子にしてあげたい。
まあ、子供の性格もあるから、一概に同じ事をしたらそうなるとはいえないかもしれないが。
Yちゃんのお母さんは「これでまたピアノの練習が出来なくて、先生に申し訳ない」とひたすら恐縮していたが、私はそれよりYちゃんがブラウン管に映ることを楽しみにしているのだ。
だって歌も踊りもピアノもみんな"音楽"だものね。 |
|
|