| 今週は、前回の"あさき夢見し"のエッセイを読んで下さった父兄に、「先生、平城京時代のマンガも面白いですよ!」と里中満智子の"女帝の手記"5冊と"長屋王残照記"3冊を借りた。
日本史は嫌いではないが、よく分かっているのが、平家以降、鎌倉時代に室町、戦国時代、江戸時代で、平安時代は多分大河ドラマでもあまり取り上げられないせいか苦手だ。
まして、奈良時代は名称も大陸の影響大で、漢化されていて難しいから、名前が麻呂だとか、皇子、新大部、県犬養などなど。
平安時代の雅びな世界より、さらに堅苦しい大化の改新以降、奈良時代は覚えるのも難しかった記憶があった。
しかしこのマンガは、分かりやすい上、史実に忠実で歴史小説を見ているようだった。
あの長屋王の変が、「なるほどこういうことだったのか」と知り、そのエリート皇族の長屋王が謀殺される場面に至っては絶句。その後、何もする気が起きず、ショックでぼーっとしていた。
(私の中では、生まれも育ちも良い、清廉潔白な長屋王=ヨン様くらいの勢いだった!)
これを描いた里中満智子は、我々と同年代で、親に漫画家になる事を猛烈に反対されたそうだ。
NHKの"親の顔が見てみたい"に出演していたが、彼女は、隠れて漫画を読み、漫画家になる為、親を説得する為に、猛勉強したと言ったのを聞いた。
確か東大にも行けるくらいの成績だったのではないか?
そんな彼女の書いた漫画だから、違うのか?とにかく、最近の漫画家は、勉強家だ。
恐るべし、漫画家!
この漫画は、大化の改新以降、実権を握った藤原一族が、如何に皇室に取り入り血縁関係を結び、その上、純血の皇族を廃して、その我が世の春(400年続く藤原王朝)を築くまでを描いている。
もちろん天皇を担ぎ上げ、大義名分をうちたてて、策略と謀略の限りを尽くすのだが。
現代でもそうだが、太古の昔から天皇の家柄、血筋というものは尊重されてきた。
その中に外から、皇室の血筋に強引に入り込み、権力を我がものにしようと企む藤原一族。
実権を失い、人間性を破壊されていった、弱い人格であった聖武天皇が、ひたすら仏教にすがり、大仏を立て、その魂に救いを求めていったのが興味深い。
一方、藤原直系の血筋である、聖武天皇の妃、光明皇后は、弱い天皇のかげで、藤原家を盛り立てようと、貧窮者の救済、社会事業に精を出し、民衆の為に働き、民の絶大なる支持を得た。
面白かったのは、今も奈良に残る東大寺の大仏も、国分寺、国分尼寺、興福寺の五重の塔、正倉院に代表される、奈良時代の仏教文化である天平文化が、何故このように花開いたのかというミステリーが分かったことだ。
要は、皇室に強引に、藤原家から皇后を立てようとした事に反対した天皇の直系であるエリート中のエリート長屋王が、無実の濡れ衣を着せられ、藤原四兄弟に謀殺され、一族皆殺しされる。
しかしその6年後、天然痘の流行病で、その謀殺者の四人が、次々と月日をあけず死にゆく中、恐怖におびえた聖武天皇と光明子が、ひたすら死を恐れ、仏にすがり大仏や寺社仏閣をせっせと建立し、我が身に呪いが迫らないように仏に願ったという訳なのである。
(ついでに遷都を繰り返すのも、呪いから逃げたわけで。)
こう思うと、なぜか大仏も寺院も親しみを帯びてくるのが不思議だ。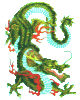
歴史の先生はこんな風に教えてはくれなかったから、京都も奈良もお寺を回ってみていても、お土産しか頭になかった訳だ。
今週は来る高校生、来る高校生に、「天平文化が花開いた訳、知っている?」と問いかけ、「知らないの?」と確かめたら。「実はねぇー」と一席演説ぶってからのレッスンだったから生徒も迷惑だったに違いない。
しかし、臆病な聖武天皇が、皮肉にも、仏教にすがったおかげか?ご利益か?藤原王朝はその後400年続き、藤原の道長の時に全盛期を迎え、あの有名な句、
この世をば 我が世とぞ思う望月の 欠けたることもなしと思えば
(この世は私のためにあるようなものだ。満月のかけないように私の思うようにならないことはひとつもない)を生む。
この道長が、あの紫式部の光源氏のモデルといわれるのだから、歴史って面白いではないか?
いにしえの奈良の都の八重桜 けふ九重に匂ひぬるかな
に代表される、奈良の天平文化がこんなに人間臭く、そして生臭かったかと思うと、奈良の大仏も、東大寺の正倉院も、そして数々の寺社仏閣も、ただ歴史の遺物としてではなく、各々過去の人間の生き様の証として、私の中でよみがえり、いとおしく思えてくる。
要は、歴史上の偉大な遺産が、とどのつまりは一個人の贖罪の証だったとしたら、これは皮肉と言わず何と言おう。
奈良=鹿せんべいとしか、この年まで興味のなかった自分も情けないが、しかし遅ればせながら、知るチャンスが死ぬまでにあってよかったと思った。
確かこの本を貸してくれた生徒は、昨年のピティナで奈良に行ったような気がする。
私は前回の京都に続き、今奈良に行きたいと思う。
中学の時、修学旅行に行った京都、奈良、大阪は一体何だったのだろう?
知らないということは不幸である。
大体、今年ピティナの審査で奈良に行きながら、まっすぐ寺院も見ず、さっさと帰っていたのだから情けない。
『あなどる事無かれ、漫画!』である。
いずこの高校の歴史の先生方も、歴史漫画を読むように勧めている訳が分かった気がする。
最初はとっつきにくいが、是非中高生にお薦めだ。
私はといえば、これから行くべき『極楽浄土』とやらを、仏教を通してもう少し勉強したいと思うのだ。
日本史の説明で長くなったが、何事も好奇心である。これが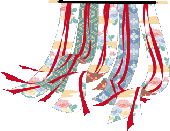 若さの秘けつにもなるらしい。 若さの秘けつにもなるらしい。
「感動する」ということを、しないとホルモンの分泌が悪くなり、実際、医学的にもどんどん老けるそうだ。
『興味』『感動』は、若さの必須条件だとテレビでもやっていた。日本史も音楽でも常に感動する為に、あらゆる興味のチャンネルを持って、好奇心を満たす事は、人生も豊かにするに違いない。
お坊さんのいう「カチコチ」は怖いが、ビクビクしても始まらない。
毎日楽しく、生き生きと生きてこその人生。
今年もあと少しで終わる。
今年は仏教が締めくくりとなった。 |
|
|
|
| 漫画源氏物語を読んだ。
普通は、漫画を読んでも眠くならないのに、これを読み出すと眠くなるくらい細かい描写、表現の多い漫画だった。夢中で読んでいたら、すっかり平安時代にタイムスリップしてしまった。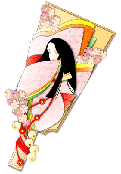
この時代は、とにかく皇室の系譜をしっかり頭の中に入れておかないと話が進んでいかないので、ボーッと読み進んでいてはいけない。ほとんどが親戚縁者、元をたどると近親である皇室の系譜だが、微妙に外からの血筋が入る中で身分の高低がついている。
それにつけてもご存知の通りの男社会、一夫多妻が当然の世界なのだが、それが男の特権というよりは、より多くの子孫を後の世に残すという意味を持っているから当然なのであり、妻一人にしか振り向かない殿様は、困りものだったようである。
今でさえ雅子様は御懐妊?と週刊誌でもてはやされる時代だから、当時の貴族の社会では女として帝や身分の高い男性にみそめられ、まして世継ぎを産むということが、如何に重要な事であったか?である。
それによって、ひいては女性側の一族も繁栄していくわけであるからだ。(かの中国の玄宗皇帝の妃、楊貴妃もそうだったように。)
そうなると娘を授かったら、より身分の高い殿方にみそめられるよう、美しくあることは一番なのだが、それだけでは無く、教養高く、上品に大切に育てあげて、商品価値を上げていく訳である。
要は、女は嫁いだ男次第という訳で、今のように一人で「自立していく」、「生きて行く」などということはないから、まさに男尊女卑としか言いようが無い。
しかし、源氏物語を読んでいくと、女性の性格がただのお人形さんではなく、意外に各々個性的であることに気付く。結局今の世とあまり変わることなく見えてきたから面白かった。
古文でもよくテストに出る、女談義のくだり。
・・・あまり上流の姫などは、まわりにかしずかれ、欠点なども隠されてしまって面白みありませんね。
評判を聞いて出掛けていくと、おやと思うほど出来の悪い姫君であったりすることが多いのですよ。
また、あまり身分の低いものもやはり気の知れぬところがありましてどうも・・・
やはり中流・・・地方の物持ちや、地方の受領の女たちの中に、思いがけず優れて個性的なのがあって、面白みも一番ですね。
やはりこれからは中流の時代でしょうな。
しかし面白みがあるといっても、遊びでなくて妻に選ぶとなるとまた大変です。
やさしい女は情に流されて、浮気をしかねないし、しっかり者は、がさつで色気に乏しく味気ない・・・。
嫉妬深いのもたまらないが、さりとて嫉妬さえしてくれないとなると・・・。
相手の愛情も疑いたくなろうというもの・・・
あまり可愛いばかりで、愚かな女というのも困りものですが、私の妻などは教養深い女学者とでも言いましょうか・・・。夫としては気のはる毎日です。なにしろ、寝物語が漢文の講義で・・・。
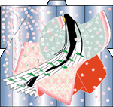
子供のころは、ふーんと、訳が分からなかったが、なるほど現在と変わらないではないか?
また、男がなぜ身を固めねばならないかというくだりでは、
だがいつまでも意味ありげにひとり身でいると、何かと誤解を招くこと多いし、散々高望みをして揚句の果てに、つまらない女とずるずるいっしょになったり、気ままな身分だと言って、好き放題するのを抑えてくれる妻というものがない男というものは、分に過ぎた恋をしたり・・・。
相手をも自分をも傷つけてしまったり・・・、終生の悔いを残すことも多いのだ。
・・・ま、相思相愛で結ばれるのが理想だが、もしも、相手が思うようでなくても、少しは我慢して相手の親の気持ちを考え・・・、相手にも自分にも良いようにと考えて、末永くそいとげることだ。
それが男の愛情というものだよ。
もなかなか興味深い。
生涯独身だったという紫式部は、鋭い洞察力を持った才女だったのだろう。
またこの時代の習慣も面白い。
文のやりとりは、小枝に結んでは和歌を贈る。その歌のセンスと、つけ文の仕方で、その送り手の知性、教養、センスを競う。
香のセンスも同様である。いろいろな香を調合させ、その人の個性を競う訳である。
独特な香合わせによって、いかに回りを魅了していくかだ。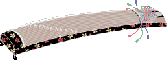
和歌のセンスや香のセンス、容姿の美しさだけでなく、更に楽器を嗜む事も一つの大事な教養だった。
しかし何より大切なのは、人間性である。六条の御息女の様に、全てが完璧でありながら、嫉妬に狂い、生霊、死霊となってしまう女性もいるのだ。
可愛いく、すねたり、やきもちを焼くくらいが男性には心地よいらしい。
知性教養がありつつ、取り澄ましていても。心の底にあるドロドロとしたものを持つ女性は空恐ろしい存在であるという訳だ。
当代きっての美男子で、プレーボーイの光源氏が、永遠の理想の女性像を求め彷徨う姿は、大変興味深いし、是非今の若い人たちにも、今後の参考に読んでもらいたいものだ。
また、日本の文化を再認識することを出来た事も良かった。
今までこそ、京都に旅すると、多少垣間見ることの出来る世界だが、日本の四季の美しさや日本人が既に忘れてしまった、奥ゆかしい文化に触れることが出来た。
ITの時代、携帯で一瞬にして笑顔マークで送信完了!こんなスピードの時代に生きていて、和歌を小枝に託し、思いを伝えるなど何と雅で風情のあることだろう。
「京都の人は心と言葉が違うから要注意」と言われるが、源氏物語を読むと、まさに心の内を顔に出すということこそ、野暮ってものだという事に気付く。
そこはかとなく漂う気配や、ムードで相手の心理を読み取る。見せかけは常に冷静沈着でありながら、物腰やちょっとしたしぐさで相手の心を推し測るのだ。
これぞ面映ゆく、奥ゆかしい世界でなくて何であろう?
江戸っ子気質で、何事もはっきりして欲しい私などは、無縁の世界だったので、すっかり雅びな世界"京都"に憧れてしまった。
また、何世紀経っても男と女のテーマは永遠だと思った。
かの恋愛小説で有名な渡辺淳一も言っていた。
「僕が男女の愛を常にテーマに取り上げるのは、このテーマが、永遠だからだ。」
人間の経験は、次の世代に教訓として伝わる事はあってもその失敗は未来の子孫が回避できない事である。
科学は進歩し続けるが人間の、こと"男女関係"はなんの進化も無いから面白いのだそうだ。
常に歴史は繰り返すという訳だ。男と女に方程式はない。平安の昔から、理想の女性像も男性像も有りながら、皆それに辿りつくことはないのだ。という事なのだろう。
愛が月としたら、満ちては欠け、欠けては満ちるという事ではないだろうか?
決して満月は続かず、月が欠けて無くなる事もない。人の一生は短い、まして愛し愛され、男女として、ときめく時の短いこと。源氏の"あさきゆめみし"は、永遠の愛を求めて、最後に、源氏が追い求めた愛のむなしさと尊さに気付く姿を描いていた。
それは現代の人間そのものであり、何世紀を経ても何も変わる事が無い。
物語は源氏の死後、"宇治十帖"へと続く。
源氏の子"薫"と"匂の宮"(兵部卿)が、幸薄い"浮き舟"を巡って、恋のさや当てを繰り広げる。
"浮き舟"は、2人の男性の間を迷い悩んだ揚句、宇治川に身投げをするが、死に切れず尼となる。
感動したのは、自分を持たないただ木の葉のように揺れ動く、はかなげで頼りない"浮き舟"が死の淵から蘇った時、「2人の男にとって自分が何であったか?」を気付き、ついには自立して強い女性として前向きに生きていく姿だった。
絵もさることながら、その場面を読むうちに涙が出てしまうではないか?
これぞ紫式部が目指していた理想の女性、いや人間として女が男を頼らず、自立していく姿なのだと胸を打たれずにはいられなかった。
光源氏の"あさきゆめみし"同様、"浮き舟"の自立に感動したのは、これも私が年をとったせいだろう。
若い時は、きっと分からなかった事だと思うから、今の若者にいくら力説したところで、その子も私の年齢にならないと、結局は分からないのだろう。
これが渡辺淳一の言う「歴史は伝わらない。」という点だ。
微力ながら、私も音楽を通じて生徒達に将来ピアノの先生として、自立する手助けをしているつもりだが、自立というものは、あながち経済的な面だけともいえない。
何ひとつ男に頼らず、可愛げのない女も寂しいが、精神的に自立して、男性と同等である上で、女性としての魅力が加われば最高だろう。
色々な意味で、女も男も異性である前に、人間としての魅力こそ、必要なのかもしれない。
しかし、何百年も昔に、こんな事を考えていたのが紫式部という女性の偉大さであり、「源氏物語」が名作として、何世紀も読み継がれる由縁だとつくづく思った。
私が源氏物語で平安時代に夢を馳せていた時、時を同じくして、歌舞伎役者の片岡孝太郎がテレビで「和楽」という言葉を大切にしていると言っていた。
もっと和を楽しんで欲しいという訳だ。
日本の文化や文学には現代に役に立つばかりではなく、素晴らしいものがたくさんある。
もっと和に親しむ事も大切なのではないだろうか?
せめて生徒には百人一首くらい、丸暗記してもらいたいものだと思う。
ヨーロッパ文化の担い手である私だが、今週は源氏物語に触れ、日本古来の美しく奥ゆかしい文化や季節感を感じたので、秋の京都にでも旅したいと願うのであった。 |
|
|
|
| 「冬ソナ」にハマる人、ハマらない人−−その違いはどこから来るか?
冬ソナファンに「このドラマにハマったきっかけは?」と質間してみると、いちばん多く返ってくるのが「なにげなく観ているうちに夢中になっていた」というお答え。「昔からヨン様のファンで、日本での放送を心待ちにしていた」という人はごく少数で、ほとんどの人は「最初はクサい台詞に笑っちゃったけど、後半は涙なしでは観られなくなって...」と、いつのまにか冬ソナの虜になってしまうようだ。しかし、その一方で「どこがおもしろいのか、ちっともわからない」「10分で観るのをやめた」という。"アンチ「冬ソナ」派"が存在するのも事実。この差はいったいどこから来るのだろうか?人間心理にくわしい専門家にドラマを分析してもらった。
韓国の純愛物語が日本でヒットした理由とは?
−まず、「冬のソナタ」のヒットの要因について、お伺いします。
「一般に"純愛もの"がヒットする背景にはそれとは逆の風潮が社会全般の傾向として存在していることが挙げられます。具体的には恋愛の主流が"見返りを求める愛"になりつつあったり、恋愛そのものが軽くなったりといった状況ですね。実際、バブル全盛期にも、ちょっとした"純愛ブーム"が訪れたことがありました」
−初恋を描いた片山恭一の小説『世界の中心で、愛をさけぶ』もヒットしていますし、バブル期以来の純愛ブーム、が起こっているのかもしれません。では、「韓国のドラマである」という点は、人気とどのように関係しているのでしょうか?
「まず、俳優の既視感の問題が考えられます。たとえば、日本で同じドラマを作って、その主人公をキムタクが演じたとしましょう。ところが、我々にはキムタク に関する既知の情報が山のように刷り込まれているので、『キャラクター=役者の実像』という錯覚が成立しにくいんですね。どうしても、「キムタクがこの役に向いていたかどうか」というような、評論家的な見方をしてしまうことになるのですが、これが韓国の、まだ実像をよく知らない俳優ということになると、安心して感情移入することができる。これも大きな要素のひとつだと思います。また、現在の韓国は、日本が高度経済成長期を迎えたころの精神的状況に近くなっていて、これまで儒教的な道徳観の中に押し込められていた欲望や欲求が、一気に殻を付き破って飛び出そうとしている状況にある。 に関する既知の情報が山のように刷り込まれているので、『キャラクター=役者の実像』という錯覚が成立しにくいんですね。どうしても、「キムタクがこの役に向いていたかどうか」というような、評論家的な見方をしてしまうことになるのですが、これが韓国の、まだ実像をよく知らない俳優ということになると、安心して感情移入することができる。これも大きな要素のひとつだと思います。また、現在の韓国は、日本が高度経済成長期を迎えたころの精神的状況に近くなっていて、これまで儒教的な道徳観の中に押し込められていた欲望や欲求が、一気に殻を付き破って飛び出そうとしている状況にある。
そのため、日本のドラマが失いつつある『抑制VS解放』のせめぎあいが、まだみずみずしさを保っていられるのだと思います。こういった面に惹かれる人も多いのではないでしょうか」
"葛藤の物語"に感情移入を出来る人出来ない人
−「冬ソナ」は、心理学的に見ると、どのような要素があるのでしようか?
「心理学という側面から見ると、冬のソナタは"リビドーの固着をめぐる葛藤の物語だといえます。"リビドー"とは精神分析学のフロイトが名づけたもので、『だれかを愛したい、だれかに愛されたい』といった欲求の源泉になっている衝動を指します。だれもが持っている性愛のエネルギーなんですね。このエネルギーが何らかの理由で抑圧されてしまったとき、人は出口のないエネルギーを何か他のものに振り向けようとします。
しかし、その転換がうまくできないと、リビドーは本来それが向かおうとした対象に固着したまま無意織の中に閉じ込められてしまうんです。『冬ソナ』の主人公・ユジンのリビドーは"愛の対象(チュンサン)の死"というどうすることもできない現実に直面して固着し,無意識の中に潜行してしまいました。隠されているのは無意識の中ですから、ふだんは意識されることがありません。ところが、何かのきっかけがあると、この固着が本人に思いもしない行動をとらせたりすることになるんですね。
サンヒョクとの婚約バーティがあるにもかかわらず、チュンサンそっくりのミニョンを見かけて、無我夢中で追いかけてしまう・・・というシ一ンで、これが描かれています。そして、チュンサンのリビドーも事故による記憶喪失という原因によって、無意識の奥底に閉じ込められています。しかし、無意識の中にはいまだ充足されてないエネルギーとして存在しているわけですから、自分でも気づかないうちにユジンに惹かれてしまうわけです」
−そういった状況に共感できるかどうかが、ドラマを楽しむポイントになるのでしょうか?
「そうですね、自分にも同じよう経験がある、あるいはそんな抑圧されたリビドーの存在を意識の深い部分で自覚しているという人には、主人公・ユジンやチュンサンの心情が手に取るようにわかり、そこにどんどん感情移入していくことになります。しかし、もともとリビドーの固着なんていうものには縁がない。抑圧されればすぐに方向転換して、いつでもリビドーを放出して生きてきたという人にとっては、こういうドラマはいったいどこがいいのかわからない、ということになります。主人公ふたりは、ただ自分たちの勝手な欲望のために周囲を振り回しているだけのかなり迷惑な人たちではないかとしか思えないのです、これが『冬のソナタ』に「ハマる人、ハマらない人の本質的な違いといっていいと思います」
−台詞の面でも、好き嫌いが分かれているようですが・・・。「愛や生き 方に関するストレートな言葉を「クサい」と感じる傾向が、ここ20年〜30年の日本の社会では主流となってきましたが、かつての日本の社会には、そうした言葉が生き生きと語られた時代がありました。その時代を生きた人たちには、このドラマはある種のノユタルジーをかきたてる魅力を持っているのかもしれませんね。もちろん、映画やドラマは軽いノリで楽しみたいと考える人たちもいるわけで、そういう人たちにとっては『冬ソナ』は、ただかったるいだけのドラマということになります、"アンチ冬ソナ派"には、こういう人たちも含まれているのではないでしょうか」 方に関するストレートな言葉を「クサい」と感じる傾向が、ここ20年〜30年の日本の社会では主流となってきましたが、かつての日本の社会には、そうした言葉が生き生きと語られた時代がありました。その時代を生きた人たちには、このドラマはある種のノユタルジーをかきたてる魅力を持っているのかもしれませんね。もちろん、映画やドラマは軽いノリで楽しみたいと考える人たちもいるわけで、そういう人たちにとっては『冬ソナ』は、ただかったるいだけのドラマということになります、"アンチ冬ソナ派"には、こういう人たちも含まれているのではないでしょうか」 |
|
|
|
| すっかり冬ソナにはまった。
レッスンの度、私が「お母さんは冬ソナ見ました?」とたずねるので、その度レッスンは中断。訳の分からない生徒は、ありがた迷惑。練習不足で今日は叱られると覚悟して"死刑台のイス"よろしく、首を垂れていた生徒が私のナタの一撃を逃れニコニコ喜んでいるではないか?
冬ソナにはまると、何故か?同じく、はまった仲間を探し、語り合いたいものだ。
ましてまだ、開拓未踏の聖地と知れば、何とかこの世界に引きずり込んで仲間にしたいという要求に駆られてしまうのは、私だけなのであろうか?
多分そのどちらかもしれない。私はもともとしつこいタイプなのかもだ。人間好きというか?いい意味で熱い血なのだと言いたい。
しかし、ドラマなぞにはまりたくないし、興味の無い人は冷ややかだが、生徒を人質にとっている私に生徒の親は好意的であるが,影では"またか"と言っているに違いない!!仕方ない。世の中には色々な人がいるものだからしつこい私が悪いに決まっている。
このドラマは最初2003年4月BSで放送された。韓国では2002年1〜3月に放送されていた。
だから、最初にはまった人々はBSで昨年の4月。次に12月に再放送があり、現在のNHKで再々放送中(20話中、現在7話目?)
私はそのNHKの第3話を見た。初恋の人が交通事故で死に、10年後うり2つの男性と巡り合うという筋の所からだ。
最初「少女漫画風、王道純愛物語か?」フーンと思ったが、筋が気になるから第1,2話を見て、どんな初恋だったのかを知ろうということになり、生徒の親からビデオを借りた所、20話までいっきにノンストップという訳である。
当初、主人も1.2話を見たが次は"結論を見せてくれ"と最終話の20話を先に見たではないか?
理系の主人らしく、ドラマなんか結論だけ分かれば良いという訳である。
がしかし、途中が気になったらしく早送りしながら、見ているうちにすっかりはまっていったらしい。今ではパソコン(4台)の壁紙、カーステレオ等々、冬ソナ一色である
こんな見方でもはまるのだから、主人に惚れ直した。大体ドラマなんか見ない人だし、人の気持ちなど汲み取れない人間で住む世界も感性も違う人だとあきらめていたから、たった1人の息子が巣立った今、主人にもドラマで涙する感受性があると知り、この人には万が一、寝たきりになっても棄てられはしないだろうと思うと嬉しかったのである。
しかし、冬ソナに夫婦ではまったからといって、この歳で愛が再燃などとはあろうはずも無いのだが、せめて老後、共通の趣味があるということは、熟年夫婦にとっては重要な事だ。
2人で暇さえあれば毎日が再放送である。キムチチゲを食べハングル語や韓国文化について語り合いながら、"冬ソナ"の既に知っている・分かっている場面で再び「泣けるねー」なんて言い合うのだから、週末に来る息子夫婦から冷ややかな目で見られてもおかしくない。
なぜこんなに筋が既に分かった・知り尽くしているのに"冬ソナ"にずっと浸りたいのか?不思議なのは自分自身である。
最初は、筋やドラマの展開が面白くて見ていたのだ。しかし20話を見て、何か心の中に今までと違う風が吹いてきたのだ。
仕事一筋でまっしぐらに生きてきたが、このドラマからの何か大切なメッセージを受け取ったのだ。多分それは、"愛"だと思う。人間にとって一番大切なものとは?当たり前に思っていた事柄だが、大切な事を忘れていた"心"を思い出させてくれた。
また、このドラマには各所に本当にシンプルで美しい飾り気の無いピアノのメロディーが散りばめられている。そのメロディーとヒロインの涙に触れる度にこちらの魂が浄化され、やさしい気持ちになれるのだ。
仕事をする前、仕事の終わった後、このドラマと音楽に触れると穏やかな気持ちになるから不思議である。今は、心のバランスを保つのに大変重要なのだ。多分こんな気持ちは、私だけだろうと思ったら、主人も同じだというからびっくりしたし、大体はまった人は、全巻見た後DVDを買い、手元に置いておくという現象だから同じなのではないだろうか?
最近では、ペ・ヨン・ジュンことヨン様にだんだん惹かれていっている。何か気になるのだ!!もうミーハー道まっしぐら!ハングル語も気になる。あれほど嫌いだった韓国という国がとても愛おしいではないか?こうなったら韓国に行くしかない!!何とか仕事が一段落したら、主人と行きたいと思っている。
その前に東京にも韓国街というのがあるのだ。東京の大久保である。ここはまさに韓国人の街である。本格的な韓国料理が食べられるし、街から聞こえてくるハングル語、日本にいながらにして韓国気分を味わえる街なのである。東京のレッスンの前後、いつも寝てばかりの私も大久保に足を豆にして出没である。
芸能人に熱をあげた過去がない私が何故こんなになったのだろう?とても不思議だ。きっとこのドラマは誰が見てもこうなるのだろうと信じていたら、そうでも無い。50代でも何とも思わない人もいる。そうかと思うと60代でもはまっている夫婦もいる。
私の統計では、子供と30代、40代は特にはまるのに20代はそうでもない。
そうか!!恋愛に憧れを持つ年令と白馬の騎士が来ると信じて乗った筈が裏切られた年代の郷愁を誘うのか?と思いきやそうでもない。やっぱり結局はただのバカかと思っていたら、先週に続き、今週号のアエラでも東大卒のエリート主婦がはまりやすい冬ソナ、日本経団連会長、東大教授、高級官僚もはまった"冬ソナエクゼクティブ"という記事を見つけホッとした。どうやらただのバカでは、なかった。
ミニョンさんは北朝鮮のスパイでは?というエリートもいたそうだが、文化人類学東大教授によると日本の中高年に冬ソナが受けるのは、”片思い”がキーワード"だと思うという記事もあった。
今の若者は、傷つく事に敏感すぎて片思いが出来ない。振られると「何故僕じゃ駄目なんだ!」ショックを受ける。今の日本の映画やドラマは、そんな若者達にとっては、リアルかもしれないが、中高年には物足りない。
中高年世代は、相手にどう思われようとこの人が好きだという気持ちだけで充足するのだ。全く同感である。それで分かった!若い人に見せるとまどろこしいとか?はっきりしないとか?言うのだ!!今時、純愛なんて流行らないという訳なのであろう。
究極的な愛とは与えるもので、見返りを望んではいけないのだ。それを若い人に理解して貰うのは難しいことかもしれない。私だって若い頃は理解できなかった事だろう。
しかし、人は所詮皆自分の為に生きている。自分が一番大切なのである。これは自己中という意味では無い。だから自分を大切にしてくれる人が大切なのである。しかし一方、自分が好きだという思いにしてくれる人に巡り合えたら、何と素晴らしい事だろう。
それがイコール、相手が自分を好きになってくれるとは限らない。しかしどんな相手に思われようと自分が思っていない恋は有り難いがちっとも嬉しくなんか無いではないか。自分が本当に好きだという感情を持てる相手に巡り合える事、それ自体が素晴らしい事だ。
片思いが問題ではない、人生に一度でも二度でも(初恋ではなくとも)そういう感情を持て,自分自身に素直になる事が出来たら幸せなのだと思う。
ヒロインのユジンは、親や友人を傷つけ自らも深く傷ついても自分の気持ちだけは決して裏切らない、これは日本人が失いつつある"純粋さ"や"一途さ"ビジネスマン達の心を捉えた"おしん"や"プロジェクトX"にも共通するテーマなのだという。
このように我々の気持ちを捉えてしまった韓国ドラマの経済効果は莫大だという、日韓に横たわる忌まわしい過去さえも"冬ソナ効果"の前に雪解けである。まさにヨン様、様々なのだ。
海外の素晴らしい映画やドラマを日本に紹介し続けてきた岩波ホール総支配人の高野悦子でさえ、この現象を心から喜んでいるという。(彼女は74歳で既にポラリスのネックレスをしているという)
我々は決してミーハーでは無いのだ。我々の様な冬ソナファンが1人でも増えるという事は、韓国という国を理解し両国の文化交流に少しでも役立つのだと思えば、冬ソナブーム万歳なのである。 |
|
|
|
| ロードオブザリング「王の帰還」を見に行った。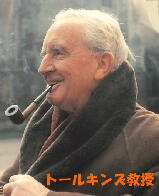
久しぶりにロードショーを見に、映画館に足を運んだ。
忙しくてもビデオは必ず見る私だが、最近は睡魔に負けてじっくりテレビを見る間もない。
映画もしかりだが、このファンタジー大長編は見逃せなかった。
第1作目も2作目もレッスンの合間をかいくぐり、劇場へと足を運び大画面でその感動を味わってきた。
そもそも「指輪物語」に興味を持ったのは10数年前くらい、東京八重洲のブックセンターにふらっと立ち寄った時だ。
私は洋書が好きで、読めもしないのにその挿絵の美しさに負け、ついつい買ってしまう。
その時はピアノの生徒に「妖精」というものを見せてやろうと、絵本のコーナーに来た時だ。「トールキンズ・ワールド」という本に目がくぎ付け、画家達の描く「中つ国」という題だった。
その時トールキンズ教授の本の挿絵を見てから、「指輪物語」の壮大なファンタジーのとりこになった。
おとぎ話の中の冒険、妖精、王女、魔法使い、この類いは私の子供の頃からの1番の興味だったからだ。
「夢見る夢子ちゃん恐怖編」とでも言おうか。「不思議なもの」とか「怖いもの」は大好きなのだ。
こういうのは前頭葉で感じるらしいから、たぶん私は前頭葉が発達しているのだろう。ちょっと恥ずかしい。
「指輪物語」は皆さんもご存じの通り、魔力のかかった指輪を無欲で争いをしない種族のホビットの1人のフロドという青年が、ひょんなことからその指輪を葬る為、命懸けの長旅をするという話だ。
その指輪をめぐって悪者が、それを手に入れようとフロドを追う。フロドはいろいろな味方の妖精や魔法使いに助けられ、魔の火山の山に向かうのだが、その指輪はただの指輪ではないので、はめたら最後、人間の悪い心を引き出すという恐ろしい指輪なのだ。
この指輪を手にすると、世の中の全てを思い通りに操ることができるという悪の権化なのだ。
筋はいずれにせよ純朴なホビット族のフロドがこの指輪を葬ることができるか、それまでの苦難と冒険が手に汗握る話の数々と映像で我々を引きつけるのだ。
大好きなファンタジーなのだが、驚くのはその映画の特撮技術。何年も前だったらとても映画には無理だったという、SFXを駆使した画面からは、それは全く作り物であることを感じさせず。まるで童話で見た、「トールキンズ・ワールド」の中を自分が歩いている錯覚に陥る。
「あートールキンズ・ワールドだ」と1人つぶやいて、劇場の中でぽつんと座っていていた。
お伽の国が存在するとしたら、こんなのに違いないと思うから映画の技術は素晴らしい。
ファンタジー、メルヘンの少ない子供は必見だ!
ハリーポッターよりずっとロマンチックで、壮大なロマンである。
この映画を見た中で、感動してメールの中に書き込んだ言葉がある。
映画を観た皆さんは覚えているだろうか。
フロドが指輪を預かり、命の危機に何度もさらされ悲嘆にくれている時、魔法使いが言う
"人は、何故こんなことになってしまったんだろうと、過去を悔やみ振り返る前に、一体これからどうしたら良いだろうかと考えよ"という言葉だった。
仕事でいたく落ち込んでいた時期だったから、その言葉が字幕に出た時は、思わず携帯に書き込んだ。人は指輪という重荷(十字架)を誰もが背負っている。それを葬るために長旅を続けるのだ。歩みを止めず、前へ前へと進まねばならない。
どうして私だけこんな思いをしなければならないのだろう?と思う前に足を止めず、これからどうするか考えながら歩み続けなければならない、そう思った。
仕事をしていて苦しい時、生きていて辛い時、悲しい時、もあるけれど、この旅はずっと生があるうちは続くのだ。
それと人は決して1人では生きてはいけない。
家族や友人、自分を理解してくれる回りの人たちの援助があってこそ、この長旅ができるのだ。
常に回りに感謝しながら指輪(十字架)を背負って生きて行くのだなぁ、と思って、最終章を見終わり、劇場を出たら、「また頑張らなきゃ」と勇気が湧いてきた。 |
|
|
|
| キーロフ・バレエを見に東京文化会館に行った。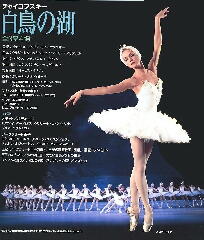
年末、各種コンクールが目白押しで息をつく間もないせいか、急に自分だけの世界に逃避したかった。
それも子供の時見た、あのチャイコフスキーの"白鳥の湖"の舞台を無性に見たくなったのだ。
なぜ白鳥の湖なのかというと不思議だ。
年末恒例の"くるみ割人形"でも"ジゼル"でもなくあの清楚な"白鳥の湖"に再会したくなったのだ。
人間の記憶とは奇妙なもので、子供の時の感動が、時折ふとよみがえってくるから不思議だ。
純粋無垢な年齢に受けた強い印象は、必ずといっていいほど、後々その人間の感性をことあるごとに刺激するのだ。
目をつむってあの青白いスポットに浮かんだ美しい白鳥たちと、バックに流れるチャイコフスキーの美しくも哀しいメロディーが、今の私の激動の毎日を癒してくれる気がしたからだ。
キーロフ・バレエといえばプリンシパルのルジマドフだ。しかし、ルジマドフは当日足の怪我の為キャンセルで代わりに代役のイーゴリー・ゼレンスキーの踊りが見られるはずだった。
バレエ通から言わせると、彼の跳躍力は超一流で、それはすばらしいそうで、しかしまたなかなか出会えないものだそうだ。
そのイーゴリーの跳躍が、見られるとあって楽しみにしていたのに、会場に着くと、当日やはり体調不良ということでドタキャンとなってしまったから残念だ。いかにバレエが過酷な肉体を酷使する芸術なのかを理解する。
跳躍が得意のテクニック派のイーゴリーと表現力を併せ持つルジマトフも同様なのだろうか。
ピアノも肉体労働だと思う時もある。その上、人前で演奏するプレッシャーは物凄いと思うが、バレリーナは唯一、肉体表現が芸術となるのだから、どれほど大変だろうか推して知るべしだ。
当日の東京文化会館は満員だった。売れ残っていた4階席の上から身を乗り出すように見ている自分はまるで天井桟敷の人々だ。
問題の踊りだが、なかなか良かった。代役のダニーラ・コルスンツェフも、そつなく王子役をこなしていたがジャンプ力は普通で、見せ場がいま一歩印象に無かったが、こちらは高く飛ぶのを楽しみにしているわけではないのだ。
しかし男性の踊りは、女性のそれとは違い、跳躍が高いと感動が大きいのだから不思議だ。
素晴らしかったのはオデット役のプリマ、ダリアパヴレンコだった。
プリマはなぜ他の白鳥と違うのだろうか?オデットと他の白鳥はすぐ区別がつく。
それは手の指の先に表れているように思った。
指先1本1本まで神経が細やかに込められていて、手首から先がしなやかで優雅なのだ。
体の細部への心遣い、柔軟さ、表現力の高さがプリマには備わっているのだ。
子供の頃、マイヤ・プリセツカヤの瀕死の白鳥をテレビで見たのを覚えているが、人間が1羽の白鳥になって息絶えたと見えたから凄かった。
しかし、何といってもバレエの素晴らしさは、音楽と密接な関係にあるところだと思う。
バレエはとどのつまり音楽を体で視覚化するためのパフォーム"芸術"だ。
音楽が無くて、くるくる回っているバレリーナほど滑稽なものはない。
ロシアのバレエを支えるバレエ学校としては、ワガーノワ・バレエ学校が有名で、ロシアのバレリーナの90%はこの学校の出身である。
ワガーノワというバレリーナは、バレエの表現力を単なる体操ではなく、芸術表現として踊りの形を確立した人である
バレエの精神、真髄を後世のバレリーナに、教え続けている人で、彼女のバレエ哲学がロシアのバレエを支えているといっても過言ではない。
彼女の信念は1つ、「高度なテクニックを体操のように単に技として見せるのではなく、まず第一にそのテクニックは、ドラマを表現するための手段である」という考え方だ。
それはいかにも音楽と共通していると思う。テクニックはある芸術表現をする手段でありその者が1人歩きする音楽は空っぽで、むなしいと思わずにはいられないからだ。
子供の頃に見たような感動やインパクトはなかったが、バレリーナの真剣な踊りと久々にチャイコフスキーの音楽に出会い幸せな1日だった。
 |
|
|