| 21〜23と韓国冬ソナツアーに行ってきた。
こんなに忙しく、命を削っている時にまたなんで?聞かれそうだが、私にとってはだからだったのである。
ピティナと共に15年以上、夏祭り、花火大会さえも一切無縁だった私だったが、人生折り返し地点も半分来てしまい、これからは明日どうなるか分からぬ身である。
忙しい中でも少しずつ自分の楽しみを大切に、心の励みにしたら、きっと生徒達にも音楽にも良い影響を与えるに違いないと勝手に解釈して、主人の休みの日に合わせ思い切って3連休したのである。
しかし22日最後の予選の子も残していたし、本選の曲が形になっていない子を残し、3日空ける罪悪感にさいなまれなかったと言ったらウソになる。
こんな大事な時にこんなことをして?と思う自分と3日くらい開けて、自分で練習出来ないようでは所詮、本物ではないと強気の自分のせめぎ合いだった!!
だから、真剣な親御さんの表情を垣間見るに付け、先生が心の内で「エヘヘ来週は冬ソナツアーだ!」なんてうすら笑み浮かべ、喜んでいる姿を想像させることは、我ながら許されなかったので、皆には丸秘だった。
前日は予選に受かっている全員のチェックを、短時間ながらしたら、夜中の12時までレッスンであった。
早朝5時半の電車に乗るので、寝られる時間はわずかだった。レッスンもこれからの旅を考えると嬉しくて元気いっぱいにこなせた。
おしゃべりな私が皆に「行ってきまーす!」と言えない事だけが、心残りだったがそれだけはどうしても言えなかった!
ここで生徒の皆さん秘密にしていて本当にごめんなさい!!
藤枝を5時半に出て、名古屋から飛行機で小1時間も飛べば、そこは韓国の仁川空港。
私にとってはこの仁川空港は、ユジンとチュンサンが劇的な再会シーンをする重要なスポットなのである。
空港ロビーをユジンがチュンサンを追い求めて走るシーンが、音楽と共に甦って来るから、もう仁川空港内ではただ笑うしかない。
主人と2人であっちかな?こっちかな?とすでにユジンになって、エレベーターを上がったり降りたり、写真を撮ったりだ。
幸せなのは、主人のはまりようも私をしのいでいるから、ちっともあきれた顔なんてしないからありがたい。
巷では冬ソナにはまった妻と、はまらない夫との離婚不仲説が問題になり、笑い話になっているが、うちは結婚して25年経つが、夫婦で共通の趣味,目的が合うのはこの冬のソナタが初めてといっても良いくらいだ。
2人で写真を撮り、馬鹿丸出しだけれど、誰も笑わないから幸せだ。
そして、今夜の夜は、あのソウルプラザホテル。
この1952室はスイートルームであり、14話でチュンサンとユジンが再会し、お互いを再確認し合う、涙無しでは見られないシーンが撮られた部屋でもあり、かつドラマ上のチュンサンの部屋なのである。
ベルボーイに部屋まで案内され、ホテル内を歩いている間も世界中に注目されているようで、気恥ずかしいやら、嬉しいやら、1回大きな声を出して笑わないとバランスとれないくらい薄ら笑い続けている自分が恥ずかしかった。主人を見ると目が笑っていたから、あちらも同じ気分だったのだろう!
大体、何故この世界に一つしかないこのスィートルームが、この日空いていたかも不思議だ。旅行会社の友人に聞けば、ここを取れるなんて稀で、本当に運が良くて、普通はめったに空いていないそうだ。
21日だけ、この『冬ソナ・パッケージ』と称した、このホテルプランが空いていたのだ。
その上でさまざまな特典がついていた、各種プレゼントあり、14話のビデオ付き、サウナ・ジムは無料、冬のソナタ・ウエルカムドリンク(OST付き)、冬のソナタ特別フルコース・ディナー付きである。
至れり尽くせりのこのプランにすでに2年で、400組の日本人が泊まったとある本に書いてあったから、チュンサン、ユジンの手垢や指紋など、もうとうの昔に消え去ったに違いないが...。それでもこの部屋に泊まれるなんて、なんて幸福なんだろう。
部屋に入ると途端、主人(うちのチュンサン)がいすに座り、ベッドに寝ようとしたから思わず「止めて!」と言ってしまったではないか?
ここはあくまで、神聖な場所だからである。かくいう私も立っている訳にも寝ない訳にもいかず(しばらくは床に座っていたが)仕方なくキングサイズのベッドの真ん中に本を置き、境界線にし、お互い一歩も近づかないで寝ようという約束をする。
何しろここへは、冬ソナツアーに来たのである!(新婚旅行ではないのである)
フランス料理、フルコースの冬ソナ特別ディナーを優雅に食べ、14話のビデオを2回見て、絶対に寝ないつもりが前日の疲れから、気付いたら爆睡していた2人で、さぞかし、イビキの大合唱だったかと思うと、「神聖」が聞いてあきれるではないか?
翌日20日は春川ツアーである。これも主人がネットで予約してあった6人コースだったが、これもなぜかこの日は我々2人に韓国人の運転手(ガイドさん)のみの3人だから運が良い。
朝の8時半にソウルを出て、春川までは3時間もかかる。途中2人(チュンサンとユジン)の想い出の地がナミソム・中島に行く。ここは1,2話でチュンサンとユジンが秋深い中、自転車に乗ったり、散策したりした場所でもある。
また雪の日のデートの数々の名シーンを生み、タイトルと共に何度も流れる感動のシーンの場所でもある。
この日は日本同様、韓国も10年ぶりの猛暑で、35度を超え、その暑さは尋常ではなかった。
汗が滝のように流れ、ハンカチは水浸し状態。炎天下の中、帽子もかぶらずひたすらガイドについて歩いた。
運動はしたいが普段は歩くこともなく、ピアノのいすに座りっぱなしの私だが、ドラマの中にいる感動で、(雪こそ無いが)黙々と微笑みを浮かべながら、歩いていられるから人間の喜びのエネルギーとは不思議なものである。
ナミソムの並木道、中道を2時間も歩き、春川市内で春川名物タッカルビを食べた。
韓国料理は大好きだ!何といっても辛いものが大好きだから、唐辛子大歓迎である。
しかし2人分と言われる、その鶏肉の多さ、キャベツとトッポッキ(韓国お餅)と共にコチジャンで甘辛くいためるのだが、とてもとても食べきれない。
それに副食として付く、キムチやカクテキの量の多さも尋常ではない。いくら大好きだからといって、はし休めに食べる量ではない。自ずと残す(韓国人でも残している)
一体あの残したキムチやおかずはどうなるか?と思うとさっさとその上に器を載せているから捨ててしまうんだろう。
"ああ勿体無い"キムチを漬ける手間と暇を考え、はしもつけずに小鉢いっぱいのキムチが捨てられるのは、"質素倹約を美徳とする日本人"としては見るに忍びない。
しかし頑張って食べたら、お代わりが来るではないか?そう韓国人というのは、全部食べると、足りないと勘違いして、おかわりを持ってくるのだそうだ。文化の違いに胃がどっと疲れてきた。
最近では、何でも残飯が韓国内でも、問題になりつつあるらしい。ものを大切にする日本人としては、この習慣、もう少し見直してもらいたい。とにかく豪快磊落ケンチャナヨ(気にしない)の食文化であった。
春川には、春川駅(チュンサンたちがキャンプに行くシーン)、遅刻をして越える春川高校の塀、そしてチュンサンとユジン大晦日の待ち合わせスポット、ユジンのお母さんの店、2人が捕まった交番、そして事故場所を見て回る。
最後にチュンサンの家に行ったのである。ここは母であるピアニストのカン・ミヒさんとチュンサンの家であるが、ここは撮影後はアメリカ人に貸していたそうだが、このブームで急遽1ヶ月前程から、市が借り上げ、一般の日本人観光客らに解放しているのだそうだ。
我々が行った時は、なぜか一人も観光客がいないではないか?
入るとあのチュンサンのピアノが『弾いて!弾いて!』と手招きしている気がしたので、思わず座り、冬ソナのテーマを弾いてしまった。
気づくと何故かカメラマンの一同に囲まれていた。聞けば、KBS「韓国国営放送」のクルーでこの日本人冬ソナ観光のブームを取材に訪れていたのだという。
おかしな日本人がチュンサンのピアノで冬ソナのテーマ曲を弾く姿は、格好の取材材料となり、ライトを浴びピアノ演奏だけでなく、インタビューまで受けてしまうことになる。
「今の気持ちは?」「ペ・ヨンジュンのどんなところが好きか?」と尋ねられる。
暑さに加え、ライトを浴び興奮状態で、何だかミーハーなことを口走る私であった。
このチュンサンの部屋は6畳もないくらいに狭く、つづく勉強部屋も3畳程。よくあんな小さい部屋で撮影されたと思う。韓国は日本に比べ、間取りが小さく、古い家が多く、一般の家にはクーラーも無い。50年くらい前の日本のような気配である。
トイレも水洗だが、紙を流せるのはホテルと空港位で普通は、ふたも無い備え付けのバケツに無造作に使用した紙を入れなくてはならない。かなりの抵抗があったが、守らないとトイレが詰まるのだから仕方ない。
そうかと思えば携帯電話の機能は日本を越える勢いだし、地下鉄はスイカが当たり前だから、IT産業の進歩はめざましいものがある。
ある本で韓国は、高度成長期の日本同様で、文化産業だけでなく、家族や夫婦のあり方も変わりつつあり、儒教の精神を大切にしていながら、だんだんとかつての日本がそうであったように、大切なものが失われ始めているんだそうだ。
離婚率は世界第2位だそうで、3組に1組は分かれるというから、感情の起伏も激しく、忍耐を美徳とする日本と違い、韓国女性の激しく泣き訴える姿を、よくブラウン管でも見るが、我慢ができない体質なんだろう。
まあ個人差もあるだろうが、独身で38歳の男性のガイドさんに「何故結婚しないのか?」と聞くと"結婚はコワイ!"若いうちは容姿が重要だが、年をとると親や自分を大切にしてくれる優しい女性でないと結婚は考えられない。
うーむ?日本の女性にとっても韓国の女性にとっても、かつての大和撫子などという言葉は死語に近く目標にしか過ぎない。男性はユジンのようにひたむきで一途で、優しい女性を求め、女性はミニョンさんのように、働く女性を理解し、抱擁力のある男性を求めているのだろう。
日本が既に失ってしまった、男女の理想的な愛の形、そして韓国では高度成長、欧米、日本に追いつき追い越せで、失われ始めている愛の形が、このようなブームを生んだのだな?と思う。ドラマとは社会や文化の流れを反映しているのだと思うと、あたら、おろそかに見ることはできないと思うことしきりである。
今回の旅は忙しい中、急ぎ足の旅行であったにもかかわらず、とても運に恵まれ、行く所、行く所でラッキーだった。こんな時期に韓国などに行って、神様の罰が当たると思ったが、こんなにまで神様が味方してくれた旅行は無かった。
もしかして、今年の夏の運を全部使い果たしてしまったのかなぁ?と思うくらいだ。そういう意味ではあとが怖い。
帰ったら死に物狂いで仕事をすることを誓う。
ニンニク料理スタミナ料理をいっぱい食べ、1キログラムも太ったことだし、
リフレッシュしてさあピティナ本選や他各種コンクールに向け最出発だ! |
|
|
|
| 今週は先週の多忙が祟ったか、3日3晩肩こりから来る偏頭痛に悩まされた。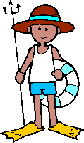
ピアノをずっと生徒と弾いているせいもあり、腱鞘炎で右手が痛くて上がらない。
(139枚の講評書きのせいもあり)
大体忙しい時は、何とかなるのに一段落すると疲れがどっと来る。毎夏の事なのだが、年のせいもあるのだろう。
こう頭が痛いと、くも膜下出血でぽっくりいってしまうかも?と思い、主人に保険証券の在りかを指示したりしてしまった。私が死んでも、もう息子は成人したし、悲しむ人はピティナの本選直前に先生を失った生徒と受験生くらいなものだろう。
主人は一人でも充分生きて行ける人だし、普段も妻らしい事もやってあげられてないし、などと悲観してしまうのは、やっぱり気力と体力の落ち込んだせいだろう。
こんな時は同業者の先生にメールする。すると、あちらも「死にそうだ!」「いやもう既に死んでいる!」とメールが来るではないか?音楽家、いや芸術家という人種は、大変大袈裟なので、お互いツーカーでその気持ちが良く分かり合えるから、端からみると滑稽かも知れないが、本人達はいたって真剣なのだ。
しかし、殆どが実際くたばっていた。お互い愚痴を言い合いながら、励まし合うことしきり。友人曰く、ストレスが、溜まりに溜まってこうなったら、「今のベンツを一千万円のにグレード・アップするぞ!」おーっ、スケールの大きいストレス発散?
聞いているだけでスカッとするではないか?小心者の私などは、そんな事はとても出来ない。せいぜい、食べたいものを求めて東京のJRを乗り継ぐくらいだ。それも古奈屋のカレーうどん、美々卯の鴨南、筑紫楼のふかひれそばと麺食いに徹している。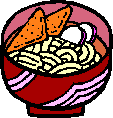
本格フランス料理やらなどと贅沢ではなく、忙しく時間の無い身に好きな味を求めるくらいで、せいぜい庶民の贅沢である。
話は戻るが、頭痛でもレッスンは、休めない、週末は地元静岡予選があり、これでほぼ全員の予選が終わる、山場中の山場だからである。
こうなったら、最後まで生きて生き抜くしかないと、薬局に走り、にがり入りの黒酢、シーカーサーの原液ジュースとリボビタンゴールド一箱を購入。のどが渇く度にこの黒酢を飲めば体内血液サラサラ効果だ。
その上、抗酸化防止のビタミンCにシーカーサーの原液を流し込み、にんじんジュースを飲み、ビタミンCとEを取ればこれで完璧ではないか?
あとは、カルシウム入りヨーグルト・ジュースでイライラ防止、これをひと揃え、飲んだら何だか気持ちも安定してくるから不思議だ!
薬が効いたのか?ドーピングのお陰で週末には、また元気になってきたから私って根は、丈夫?既に死んだ筈の友人も、週末には青梅での審査の為に復帰していたから、ユンケル片手にしっかり生き返ったに違いない。
「先生はいつも強靭な精神と肉体ですね!」などと言われると嬉しくない。責任感が強いと言って欲しい、まして「好きな事、とことんやれていいわね」なんて言われると頭に来る。
「好き」などという限度は、とうに越しているではないか?「やるしかない」のである...。
今年こそのんびりした夏を過ごしたいと思いつつ、生徒に「今年の夏は頑張りたい!」と言われると「一緒に頑張ろう!」と手を取り合っているから、バカなのである。
しかし、お陰さまでA2・1名、A1・1名、B級・6名、C級・4名、D級・2名、E級・3名、F級・1名、グランミューズ・1名、総勢19名の本選決定だ!
わずか数名取りこぼしはあったが、反省として受験前に親子共々、多少の迷いがあった生徒は、やはり最後の最後でアクシデントに見舞われやすい。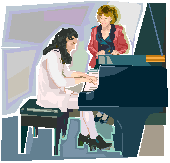
この様に予選のレベルが上がってくると、実力とは別に少しの気の緩み、迷いは命取りなのだと実感した。
それにしても、ほとんどの生徒が2回ずつ受けたから、6月中旬から7月中旬まで40回以上の予選をやってきたことになる。頑張った自分に「ごくろうさま」と誉めてあげたいところだ。
しかし、あと30回以上の本選が8月中旬まで続くのである!!汗・汗である。
とにかく最後まで、どの子にも悔いの無い演奏をさせる為の手助けをしなくてはならないと、自分に叱咤激励しながらの毎日である。
(来週は、お待ちかね冬ソナツアー日記です、乞うご期待!!) |
|
|
|
| 今週末はピティナ・コンペの奈良後期予選の審査だった。
その前に今週は東京を2往復した。午前中に東京でレッスンをしていて、午後は何事もなかったかのように普通に静岡にいてレッスンしている。
こんな事が出来るのは、子育てが終わっている事。ほとんど主婦らしい事を夏の間、放棄している事。主人の協力あってこそなのである。
うちの主人は仕事で帰宅も遅い(大体10時すぎ)から2人で夕飯を食べるのが11時である。
その上、あまり食べ物にうるさくないから、非常に楽である。(忙しい時は重宝な人である。)その上、ひとりでいる事が大好きな人なのだ。
奈良に出発する日は、超過密だった。朝5時半に起き、東京に行き、予選を受ける子のレッスンをし、お昼にとんぼ帰り、、明日の予選を受ける静岡の生徒の最終チェックをして、夕方6時の新幹線で京都に向かった。
京都駅に着くと、京都にいるという実感を味わいたくて、美々卯の鴨南蛮そばを食べに京都伊勢丹に行く。こんな時間(9時半)でも、レストラン・フロアーは、開いているからだ。
関西はとにかく薄味だが、だしが最高だ。あのだしを味わうだけで、体中が幸福なのだ。しっかり一人幸せに浸り、JRで1時間ゆられ、奈良に向かう。
奈良のホテルに着いたのは、夜11時前、NHKの冬のソナタ14話にスレスレ、セーフ。
しっかり、また浸ってから寝るのだ!でも忙しい日は、興奮してなかなか寝つけない。
朝はロビーに、9時に集合だから慌ただしい。その上、審査は朝10時から夜9時まで、人数は139名もいる。
果たして139枚講評用紙を書ききれるか?気力で頑張るしかない。
今回は、以前何度もご一緒したことのある、U短大のA先生なので、久しぶりにお会いできるのが楽しみだった。
奈良は中学の修学旅行以来だ!
鹿せんべいを鹿にあげたのが、ついこの間のようだ。確かあの時も主人と一緒だった、(主人とは中学の同級生同志なのだ)なぁ、などと感慨深げに、うちの「チュンサン」も年をとったと思いつつ、「お互い様」なんだろうとも思いつつ、審査会場に向かう。
奈良は、秋篠音楽堂で近鉄百貨店の中にある立派なホールだ。
高レベルの栃木の矢板コンペの記憶が新しいので、さて関西のレベルはと気になるではないか?
A2、A 1、Bまでは、高得点を取る子と、そうでない子がはっきりと分かれていたので、審査も楽だったのだが、問題はD級だった。14名参加中、本選参加は4名なのに、高得点者が9名もいたのだ。
D級というのは、中1、中2対象である。昔は、「黄昏の中学生」といわれ、思春期である上、クラブ活動や試験に追われ、いちばん低レベルといわれる級だったというのに、ここは凄かった。
8.5が3枚、8.0が2枚で、優良賞なのだから、いかに高いレベルの競争だったか?である。
さぞかし落ちて、点数を見た生徒は、悔しかったに違いない。
コンペは絶対評価でありながら、人数制限があるので予選通過者は自ずと相対的評価で決まってしまう。要は、相手次第なのである。
支部の方に聞けば、上手な子は奈良県外、大阪からの受験者が多いそうである。栃木矢板もそうだったが、上手な子は埼玉や都心からだと言われた。
かく言う、うちの生徒も地元静岡ではあまり受けない。友達と重複する事、テストや学校行事の時期を避けて、山梨や東京、名古屋、遠くは大阪、京都と遠征しているではないか?
各地レベルの高い低いは予想を立てられないから厄介である。今はNetで、各地の予選通過ラインが発表されるので、前年のレベルの高い所は敬遠される。
その裏を読んで、またそこに残るなんて読みながら、各々に移動していくので、結局情報に振り回されるわけだ。
「音楽は競走ではない」、とかくいう私も、高得点をとりながら落ちてしまうと、もう少し情報収集をするべきだったと後悔しきりである。
こうなると、もう普段から、自分の実力を上げていくしかないのだ。そうしなければ、生き残れない予選になってきた。
朝10時から午後4時ごろになると、腕の付け根が熱を持ち始め、集中力も切れてくる。
もう駄目だと思う間もなく、次の子が始まるので、止めるわけにはいかない。
休憩は1時間に10分あるが、トイレに行ってフッーとしたら、また出掛けて、せっせと講評と、点を記入しなければいけない。
しかし、自分の生徒も今頃、同じ立場で舞台に立っていると思うと、私も真剣である。最後には文が支離滅裂になりかけていた。昔、審査中に倒れ、亡くなった先生がいたのを思い出し、ふと不安になる。
そうだ休憩中には、いっぱい水分を取って、血を薄めよう!とお茶をたくさん流し込むように飲んだ。
しかし、上手な演奏を聴くと、疲れがとれるから音楽とは不思議である。どんなに上手でも、うるさい音楽やキィを叩いた音楽は耳障りだから、疲れてくるとかえって本物を見分ける力がついてくるから不思議だ!
最後の審査の結果を出したら9時過ぎだった。
こんな地区だから、講評も表彰もなく、掲示発表だったので、舞台に立ち、何か一言話さなければいけない余計な緊張がないのが救いだった。
それと、お昼のお弁当がおいしかったこと。大阪・京都の審査はお弁当が豪華版で、大体2段弁当!1段目は白いご飯に梅干し、赤飯、柿の葉ずし、笹の葉寿司が入っている。とても食べきれず、ホテルに持って帰ることにする。煮物も薄味で、上品な味付けでとても美味しい。
楽しみは食べることなので、とっても幸せだ!
今回の審査で、気になったのは、子供たちのフランス音楽に対する理解が、いまひとつだったということだ。
フランス音楽を日本に紹介した、初めての先生はかの故安川加寿子先生だ。
先生は、フランス音楽を一言でいうなら『エスプリ、ムード』でしょうとおっしゃった。エスプリとは英国ならジョーク、これは冗談ともつかず、おしゃれな会話、少々の皮肉を込めた(軽妙洒脱)、しかし、痛烈でないしゃれた冗談。
ムードとは、その名の通りエレガンス(優雅)に代表される、何とも言い知れないハーモニーの世界だろう。
今回のC級ではイベールに、D級でドビュッシーに、Eではプーランクに、Fではラベルにフランス音楽が登場していた。
皆、真面目にそのまま弾くので、イベールのしゃれたムード、プーランクのサロン風の音楽、ロートレックの絵のようなサーカスや道化、そしておしゃれな気取りの世界、風刺と皮肉を込めたドビュッシーのゴリウォークが生きることなく、ただ弾かれたことだ。
残念だが楽譜通りでなく、その作曲者の背景や、生きていた時代、国民性や文化を理解していないと難しい上、フランスのおしゃれ心を理解していないといけない。
中にはドビュッシーをテンポで揺らし、気まぐれを表現している子もいたが、CDを聴いて真似したのか不自然になってしまう。さしずめ、外国人が歌舞伎を演じている感じなのかと思う。
狙いはわかるが...。
「センス良く」という基準はとても難しい。本や紙にも書いてないからだ。センスとは勉強するものでは無く、磨くものだから。
印象派の絵や音楽、色々なものを見たり聞いたり、普段からセンスを磨くことがないと、この手の近現代曲は自分のものとして、表現するのは難しいと思う。 |
|
|
|
| 静岡は、今週大雨洪水警報が出た。すごい雷雨だった。
私はといえば午前中は、うつらうつら、ぼーっとしている日が多い。というのもかなりの低血圧で、上さえも100を越えることなどない。
レッスンが始まる3時頃には、今日こそ、もう体が重く動かないと思う日が多いのに、仕方なく仕事を始めると、夜に近づくにつれ絶好調だし、夜はめったに眠くならないので、寝るのはいつも2時か3時だ。(たぶん血圧が上がるのだろう)
しかし、いったんスイッチを切ったが最後、午前中は死んだも同然なのである。
それでも今週の様に、土日に東京へ朝5時半過ぎ起きで出掛けた時には、元気良パッと跳び起きられるから、自分では本当は怠け病と思っている。(生徒がピティナを受けるので1週間レッスンを空けたままではあんまりなので。)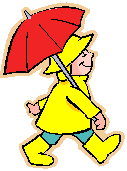
お母様方は"先生は責任感がお強い"などと褒めて下さるが、私から言わせるとただの小心者、臆病者で、子供を信じ切れない所があるだけかもしれない!
問題の雷雨は、どうも全国から見ても静岡、特に藤枝に集中していたらしく全国の友人から「先生大丈夫?流されていない?」と心配のメールや電話を頂戴した。
『流される』と聞くと、さしずめ高台に住む私にとって、今の心境はコンペのノアの箱舟に全員乗せ切れるか?という感じである。
とりあえず、A2級1名、B級6名全員乗せることに成功。あとはA1〜Fまで、他の級は半分ずつ乗せたが、まだまだこれからである。
1人も取りこぼしてはならないので、気力・体力勝負だが、体力が弱くなると、なんだか時折自分のやっていることがむなしくなるのは毎年の事だ!
いずれこの苦労も後1.5カ月で終わるからとカレンダーをにらめっこして、頑張る日々だ。
体力が落ちると気力がなくなり、親御さんの各種悩み事の相談、受験の相談も受け入れるキャパがなくなるのだ。
午前中はごろごろして、鰻の肝焼きなどを栄養剤で流し込みながら、午後に備えている日々である。(もちろん冬のソナタのCDを聴きながら、心をリラックスさせてもいる。)
最近そんな中で、感じることは少子化のせいもあるが、親子一体型がとても増えている気がする。これはうちの教室だけでなく友人のピアノの先生方といつも話題に上ることだ。
それがコンペという非常事態によってクローズアップされてくる。
いわゆる子供の成績で、親が一喜一憂する姿を見るにつけ、感じることだ。
子供が、コンペでどんな形にせよ失敗する事は、頑張ってきた親子ほど傷は大きい。しかしその経験を、いつもポジティブにとらえ良い経験に結び付けている親子と、そうでない親子の違いはやはり一言でいって「愛」なんだと思う。
子供を本当に愛しているか?というシンプルな質問はありきたり過ぎているが、実際本当に子供を愛しているのだろうか?と思う場面に時々遭遇する。
子供の欠点・失敗・長所をすべて認めて理解し受け入れ、温かく見守るなんて当たり前のような事を、皆やってそうで実際にやれてない気がするのだ。
親として、子供が失敗するのを見たくない、経験させたくないと思うあまり手を出し過ぎて自分で考える力を奪ってしまうのは愛だろうか?
自分で判断出来る子、自分で考えることの出来る子、に育てるのが教育なのだと思う。
ライオンは谷からわが子を突き落とし上ってきた子のみ、育てるという話があるではないか。
思春期の子供たちは親の言うことは勿論の事、先生の言うことすら、言い方によっては受け入れてくれないから、まるで腫れ物に触るようなレッスンになってしまうから、思ったようにいかない。結果はこのおのずとコンペの点になり出てきてしまう。
それをご機嫌取り取り、ビクビクしながら教えるのか?ビンタの一つもお見舞いし、いうことをきかせ、点を取らせた所で、一体何になるのだろうと最近は思う。
やる気のある素直な子だけ、延ばそうというのではなく、子供の年齢、タイプによって伸びる時期、のび悩む時期があると思う。
多分、親も先生も熱心なら、成績は子供が「素直にやるか?やらないか?」にかかっているだけなんだと思う。
私の統計では、大体小3まではよいが、小4頃から思春期の中学2−3年までは、本当に親も子も悩んでいる。
しかし「愛」していればその期間、無駄な様な事も待ってあげられると思う。
決して親の見栄や欲で子供を見ず、その子の全てを(甘やかすというのではなく)受け入れることができれば、コンペを受けることで、結局音楽の道に進まずとも、親子や先生との信頼関係を築き、何事も頑張る事の大切さ、駄目だった時は、自分の甘さや欠点に気付く良いチャンスを与えられると思うのだ。
子供は親の従属物ではないのだ!
いつも文句も言わず、素直に無心にひたすらピアノも勉強にも向かってほしいと思う。
これこそ親のエゴだと思う。子供だって日々葛藤して、悩みながら生きているのだ。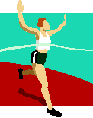
私はつくづく最近親のエゴの手助けをしたいとは思わない。
音楽は情操教育であること、コンペでは最後まで頑張る事の大切さ、達成感、音楽の奥の深さ、そしてなにより集中力を学んでほしい。
8月からオリンピックが始まる。体育スポーツ、大の苦手の私でもひたすら無心に競技する選手を見て感動するのだ。
オリンピックは『参加することに意義がある』というが、親子でコンペに参加する意義を是非探してほしいものだ。 |
|
|
|
| 6月中旬から、毎週生徒がピティナの予選を受けている。
毎年の事ながら、年々予選通過レベルが高くなると、この程度弾けたらいいだろう?とこちらが油断したら最後である。
結果で後悔しない為にも、子供の最大限の力を引き出し、送り出してあげないとならないので、受験日を迎える週末のたびに精魂つき果てる。
生徒も親も大変だが、それでも自分の受験する週は1度だが、こちらはずっーとだから、たまったものではない。充電どころか?気の休める週が一日も無く、週末になると、更に過密スケジュールだから、まさに「つきっぱなしの電球状態」が夏中続くのである。
体力、気力が勝負の夏本番である。
今年はそれでも「冬のソナタ」にはまったおかげで、ピアノの空き時間は心穏やかに過ごせるので、コンペのある夏の間はなるべく、「冬のソナタ」から覚めてしまわないように心掛けている。
そうすれば、いつも子供たちに優しく接していられそうな気がするからだ。
一喜一憂してはいけないと言いつつも、必死で教えたのに言った通りやってくれなかったりすると、ついつい頭に血が上ってしまうのは親御さん同様、私も一緒だからだ。
最近は冬ソナの主題歌を歌うRyuや、韓国の歌手に興味が湧き、サントラ盤はもちろん劇中に挿入されている、隠れた歌手の歌を時間の合間に聴いているが、これがなかなか良いのだ。
まだまだこんなに美しくシンプルなメロディーが、この世に存在していたのである。この新鮮さが韓国の音楽の特徴なのである!
心が洗われるひたすらシンプルで美しいメロディーと、冬景色を心に刻み、暑い夏の試練を乗り切る毎日である(汗)!
今日はそんな中で、「冬のソナタにはまる人、はまらない人」という記事を見つけたので紹介したい。
興味のある人はエッセー集を見て下さい。
それと掲示板、N先生の投稿も合わせでご覧ください。
N先生は私の尊敬する友人で、某国立大の教授で、ピアニストです。
とても興味深い内容と、短いですが真に教育の目指す目的を書いてくださったのが、印象的ですのでぜひ読んでみてください! |
|
|