| 2 月15日ロードオブザリングを見に行きました。 月15日ロードオブザリングを見に行きました。
感想をエッセイにまとめましたので、読んで下さい。
|
|
|
|
| 2月23日
グレンツェン・コンクール全国大会があった。
9月から始まって予選、12月の本選、そして2月の全国大会。
短い曲とはいえ半年間の間、3回課題曲が入れ替わり、それなりに良い緊張感を持続できたと思うが、全国大会はいちばん課題曲が難しくなっていた。
その上、2カ月弱しかなかったのでさらに忙しかった。
結果は、 | 小3〜4年の部 | 優秀賞 | | 小5〜6年の部 | 優秀賞:2名 | | 中学生の部 | 銅賞 | | 高校生の部 | 金賞 |
が貰えた。
特筆すべきは、小3年生のY.A.さんと小6年生のA.U.さん、この2人はお父さんの仕事の関係で各々浜松と大阪に転勤になっていた。
しかし、直前にどちらもお母さんがインフルエンザになり、レッスンに来られなかったので、Y.A.さんは2回、A.U.さんはたった1回のレッスンで、後は電話でレッスンをしたのだが、ちゃんとトロフィーを貰ったからびっくりした。
その集中力と精神力には脱帽だ。
後は、何といっても高校生のT.M.君(高2)。彼はこれで金のトロフィー3本だ。
予選、本選、全国大会と金なんてすごいではないか。本人、親御さん共に、全ては先生のご指導のおかげと喜んでくれるがそんなことはない、実力だ。
彼は、何よりも音楽が好きだがこんなにまで、彼のピアノを皆さんに認めてもらえ嬉しいではないか。
発表会にはショパンの「英雄ポロネーズ」を弾くが、こちらも楽しみだ。 |
|
|
|
| 2月8日
名古屋の津島市の文化会館にて、日本アーティスト・ビューロー主催の"ジュエリー・コンサート"があった。
これは第15回夢コン・コンチェルト・フェスティバルの受賞記念コンサートで各部門の最優秀賞受賞者とグランプリ受賞者、そしてゲスト出演の方々で構成された晴れがましい舞台となっている。
私の教室からはグランプリを受賞したK.A.(中3)さんが出演した。
曲は勿論、受賞曲のバッハの「チェンバロ協奏曲」だ。しかしこの曲は昨年5月以来、全く手付かずに置いてあった。
元々譜読みは早いし、曲想も持ち前の自然な感じであまり手を入れずに済んでいたところに、この長い休止期間があり、いったいこんなのんきな状態で良いのだろうか?
今年1月中頃になって、そろそろ本気を出して、グランプリに恥じない演奏をしなくてはとあせることしきりだった。
兎に角、立派なチラシに大きな写真入り、その上「チェンバロ協奏曲」は、彼女を初め3人も弾くではないか?
当然、比較されこそすれ、グランプリと言えば当たり前にうまくなくてはならないのだろう!
演奏家はコンクールでハラハラ・ドキドキ、入賞記念では思わぬ重圧がかかり、いつも心安らかに演奏することが無い、本当に因果な商売だと思うが、だからこそ、この緊張が良い意味で良い演奏につながるのかもしれないと思うから皮肉である。
私はと言えば、いつもただひたすらに、何かに追われ緊張している内に、何だか"人生なるようになるさ""最善を尽くすのみ"が「座右の銘」だからやることをやったら、ひたすら生徒を信じるのみと腹をくくっているのだ。
しかし、今回のグランプリの晴れがましい受賞コンサートには行きたいような、行きたくないような複雑な心境だった。
決して生徒を信じてない訳では無い。数多い私の生徒の中でも精神力も集中力も群を抜いている子だし、予選も本選もそれなりに弾いてくれた。がしかし、今回もオーケストラをバックに果たしてぴったりと決まるだろうか?あの長いカデンツをかなりのスピードで外さず、弾いてくれるのだろうか?グランプリに恥じない演奏をしてくれるだろうか?と思うと内心、気の小さな私はヒヤヒヤだったので、この日東京へ仕事で行かねばならない急用が入った時は、その場に立ち会わないで済む幸せにホットしてしまった。(K.A.さん、ごめんなさい!)後でメールが来た時は、心臓バクバクでのぞいてしまった。以下本人の文。
「先生、気持ち良く演奏することが出来ました。今考えてみると生オケと共演できるということは人生に一度、あるかないかのとても貴重な経験であり、この様な機会に巡り合えた私は、すごい幸運だったと思います。私をここまで引っ張って支えて下さった三好先生、家族、 指揮者の先生、そしてこのコンクールを主催して下さった日本アーティスト・ビューローさんに感謝したいです。」 指揮者の先生、そしてこのコンクールを主催して下さった日本アーティスト・ビューローさんに感謝したいです。」
とあった。
中3にしては大人びた文章だが、本人の心からの感謝を感じて嬉しかった!!これは大成功だったということだろう。
後で聞けば、オーケストラのメンバーが終演後、足を鳴らして演奏を讃えてくれたというし、指揮者にも後で、たくさんのお褒めの言葉を頂戴したそうだ。
彼女は将来、音楽家志望ではないが、この様な経験を人生で出来たということは、何と素晴らしいことだ。
本当に関係者の皆さん、主催者の皆さんに感謝したいと思うのだった。
私とすれば、やはり万障繰り合わせても聞きに行けば良かったと今度は、後悔することしきりだった。 |
|
|
|
| 1月31日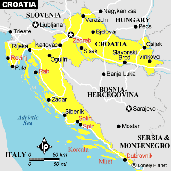
東京麻布の区民センターにて、国際交流コンサート2次審査に参加した。
この国際交流コンサートとは、いま巷でしきりに話題になっているNPO(特定非営利活動法人)の一環として文化庁の後援で「子供の心を豊かに育てる教育システム研究所」が日本とクロアチアの文化交流を図るという、趣旨のもとに開催されたものである。
何故、私がこの会に関わっているかというと、クロアチア(旧ユーゴスラビア)出身の私の姉の夫ゾラン・ヤコヴチッチが日本で交流のある音楽仲間たちとの関連からである。
昨年末、サントリーホールで開催されたジェイタイス・クリスマスコンサートもその活動の一連である。
今回は第1回目の国際交流の派遣オーディションということで、急な募集だった。
その上、私が生徒の出演の依頼を受けたのは、オーディション直前、10日前だったので、心の準備も出来ぬまま、「クロアチアに行ってみない」と突然言われた生徒は、キツネにつままれた様だったことだろう。
しかしうちの生徒は、常にコンクールで切磋琢磨されている連中だから、持ち曲は何とかなるのだ。
チャンスとはどんなところにあるか分からないが、生徒達の対応の素早さにも頭が下がる。
しかし、人前で演奏出来ることこそ音楽家、演奏家冥利に尽きることだし、そのひとつひとつが経験となり次への自信とステップになるのだ。チャンスは生かすべきだ。
結局、1時審査に中一、高一の生徒1名ずつと東京の大学に通う姉妹の生徒にオーディションを受けさせた。
結果、1次審査は無事全員パス。2次審査に進んだ。
私もこの審査を依頼され、東京に出向いた。ピティナと違いひとり15分のプログラムでゆったりと時間は流れる。
審査員はピアニスト、ヴァイオリニスト、外国人の先生、文化庁の関連の方々、他色々な分野の先生方で構成された。
2次審査は12名だった。音大生がほとんどでラフマニノフやプーランクの大曲を楽々弾いていた。
うちの生徒は海外でのコンサートを意識して、日本の作曲家のプログラムを加え、聴衆が楽しめるようにバラエティー豊かにまとめてみた。
東欧のバルトークの作品、ショパンの小曲、かごめ変奏曲、そして日本人の近現 代曲をプログラムに入れ、エンターテイメントに徹したのが良かったのか、審査員に喜ばれKKさん(中1)が見事1位になり、クロアチアでコンサートに参加する為の高額な費用の補助を頂戴することが出来る事になった。東京の大学生もデュオで2位になった。こちらも補助金獲得だ。 代曲をプログラムに入れ、エンターテイメントに徹したのが良かったのか、審査員に喜ばれKKさん(中1)が見事1位になり、クロアチアでコンサートに参加する為の高額な費用の補助を頂戴することが出来る事になった。東京の大学生もデュオで2位になった。こちらも補助金獲得だ。
急なことで、全て初めてだったので大あわてのオーディションだったが、意外な結末に喜んだ。
3月に行われるクロアチアでのコンサートがどんなものかとても楽しみである。
なにより、その後の生徒の人生において貴重な体験になるに違いないと思うと嬉しいことだ。 |
|
|
|
| 1月24日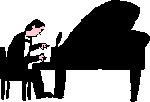
コンチェルト東京後期があった。
11日に続き、今回も初体験の生徒を連れ、また東京へと向かった。
向かうは新大塚の東邦音大。今回は第二会場が渋谷でもあり、全国的には名古屋、大阪が縮小された分、東京後期に人気が集中したことがうかがえる。
コンチェルト・ファンとしては嬉しいことだ。
初級の前日のリハは早朝、翌日も午前中から本番がある上、もうひとり上級の高校3年生(彼女は既に一般大学の進学が内定しているのだが、ピアノ大好きで趣味とはいえ、かなりの腕前である。)だが、その子は、リハが夕方、翌日は昼過ぎとあって東京のスタジオを1日2往復しなくてはならない。
前回11日には渋谷の坂を駆け回り、股関節が痛くなり、後で足を引きずる羽目になった。
日頃の運動不足と心肺機能の低下で、心臓が止まるかと思うほど走ったが、今回は平地とはいえ、東邦音大まで地下鉄を走った、走った。
聞けば、友人の先生も同様に渋谷と東邦音大を二股かけ、ゼーゼー・ハーハーしていたから、2人も生徒を出している先生は、場所と時間が違うと命懸けのダッシュを繰り返すのだ。
その友人に後で夜、電話をしたら、既に夜9時で寝込んでいたから、やっぱり2人して「年には勝てんわ」と慰め合うことしきりだった。
さて、コンチェルト初めての生徒だが、初体験というだけあって予想通り、エレクトーンのオケ伴を聞かず、突っ走ったではないか。
これがリハで良かった。「よくオケを聞くのだよ。」「あわてないでね。」と、とことん言い聞かせ、落ち着かせ、今度は大丈夫と意気揚々、翌日本番に臨んだのだが。
「あれっ?」そうは問屋が、思い通りにはいかないものである。
今度は速さが一定にならず、コントロールの利かない、糸の切れた凧のようにテンポがフラフラして定まらないではないか?
"ああー、まだ自分の音もオケ伴も聞けない"と愕然としてしまった。
思春期に突入した子供にとって、本番で色々なことを一つ一つ自分の中で消化し、落ち着いて表現するのは難しいものだと思ったが、いい勉強ができたと思った。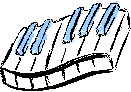
何故って、ソロでも自分の音を聞くことが基本なのだから、コンチェルトはそういう意味で自分の欠点と向かい合い、見つめ直す良いチャンスなのだと思うからだ。
後で頂戴した、かの江崎先生の講評にも、「アンサンブルは経験が宝です。よいチャンスをつかまれ、よい勉強をされましたね。」と書かれてあり嬉しかった。
上級の高校生だが、リハーサルでも細い体で、ショパンのコンチェルトの1番をよく弾いた。
彼女との数年間(彼女は帰国子女で、小さい頃はアメリカで姉が教えていた。)を想い、目頭が熱くなった。
コンチェルトの体験学習に、自身のアルバイトの大金をはたき、この日を目指し、テスト期間中もよく努力していた。親孝行で自分のアルバイトのお金で、レッスン代を工面しているのも今時立派で、頭が下がる思いだ。
しかし、残念なことに本番は弾き順が1番だった。演奏自体決して悪くはなかったが、彼女の音の美しさや、表現力が比較対象のない1番では、引き立つこともなく、テクニックのひ弱さだけがアピールされたようで残念だった。
以前ショパンコンクールで故福田靖子理事にお会いした時、私の生徒が「演奏順何番?」と尋ねられ、1番と答えたら、「それは残念。また頑張ってね」ともう結果が出たようにおっしゃったことがあった。
先日放映されたNHKでの浜松コンクールでも、出場者が予選通過出来ない理由を審査員に尋ねるシーンで、ピアニストの中村紘子が「1番に弾いた演奏者で、予選に残った人を過去に私は知りません。」と答えているのを見たことがある。
1番の弾き順で、点を取るのはこの世界では如何に難しいかということを物語っているではないか。
これは負け惜しみでもなんでもない、紛れもない事実なのだ。
こうなると運をつかむのもこの世界では大切なことなのだが、これだけは神のみぞ知るから、操作しようがない。
なんだかんだ言っても、所詮、審査は人間のすることである。秤で計った様な基準が無い所で、救われもするし、見捨てられることもあり、結局相殺だと思う。
要は、1番に弾いても魅力のある演奏が、出来なければいけないのだと思うのだ。
結果だが、開けて見たら、初級は「優良賞」を頂き、有頂天だ。
最初から体験学習とあきらめ、望んでいたからなおさらである。全国大会の通過点に0.02足りず、あと一歩だったのが惜しかったが、本人には励みになったようだ。私としてはかえって欲が出て、ちと残念。
上級の生徒は、卒業演奏で悔いが残ったが、これが終わりではないから、「ピアノは一生大好きだし、コンチェルトも大好き。またやりたい。」とくれたメールに、こちらが逆に励まされた。
これも若さの特権だろう。嬉しかった。 |
|
|