| 10/7日記、「レンブラント展を見て」の最後、「何故音楽が17世紀、富と名声のむなしさを象徴する小物(バニタス)だったのか?」
疑問に思っていたが、これを読んだ学生からも質問され、自分なりの考察をエッセイにまとめてみたので読んで下さい。 |
|
|
|
| 食欲の秋だ
今日は、お料理教室だった。
私は、数年前から懐石料理を習っている。"まあ・何と奥ゆかしい!!"と思われるだろうが。
動機は"おいしいものを美しく優雅に食べると言う生活にあこがれているからかもしれない。"
私は、何しろ焼きそばしか作れず結婚してしまった。というのも、私の母親は教育ママだったが、何故か教育方針が一貫していて、「オールマイティーな人間」より一芸に秀で出ることを「良」としていた。おかげで本を読みピアノを弾きさえすれば、家事一般は、一切免除された為、私はご飯炊きを覚える必要が無かった。 しかし、人生は甘くなかった。
結婚してたちまち困り果てた。味噌汁一つ作れないのだから毎日母親に電話しては、作り方を聞く羽目になった。それからというもの覚えたレシピは忘れないようにカード式の単語帳に作り方を記入し、それを常に持ち歩いた。おいしいものを見たり、聞いたり、食べたりする度にそのカードに記入していたから、夕飯の献立に悩むと「今日は何にしようかな?」なんて単語帳を出してはカードをめくっていると魚屋のおじさんに「お姐さん、今日も英語の勉強かい?」とよくからかわれたものだ。
ピアノの生徒が増えるにつれ時間をかけて料理を作ることが出来なくなったが、忙しいからといって手を抜けば、365日忙しいので、毎日お惣菜になってしまう。というわけで、ほとんどお惣菜を買ってくることは無い、買って来たお惣菜をテーブルに並べると家族より自分自身がむなしく、寒々しい気持ちになるのだ。
どんなに一品二品少なくて手抜き料理になろうと手作りを心掛けている。勿論夕食は、一般の家庭の様な時間ではない。早くて9時だからそんな中で息子を良く育てたと思うけれど、それでも手作りのコロッケを揚げたりしていた。
私は友人に恵まれているが、その多くは完璧な主婦だ。料理はとっても上手だ。
どんなケーキでも見事に焼けるし、家の中はいつもピカピカで季節の花が庭に咲きこぼれ、ちょっと立ち寄ると世にもおいしい紅茶を入れてくれる。
そんな生活に憧れ、そこに帰る事の出来る家族は本当に幸せだと思う。それに引き換え我が家の人達は、こんな忙しい女性を妻、母に持ち不幸だなと思わずにいられない。
その上更に友人達は料理教室に通い常に腕を磨いているのだから驚いてしまう。そんな生き方に少しでもあやかりたいと月1回料理教室に通っているのだ。
おかげで先生をはじめ、素敵なマダム達と知り合う事が出来た。
ピアノの世界に四六時中いると、どうしても世界が狭くなるが、こうして無い時間をやりくりして出掛ける事は大切だ。
何よりリフレッシュして気分転換になる。料理教室では普段出来ない様な手の込んだ料理を作り、食べる事が出来るが、時間さえあれば作る事が可能な様に先生は詳細にレシピを書いて教えて下さる。
食前酒を頂き、季節を考慮し、1つ1つ吟味された器に美しくセンス良く盛られた料理に箸をつけながらマダム達との気の置けないおしゃべりは、至福の時だ。
私の先生は、常に料理が「おもてなし」であるということを忘れない方だ。
季節、季節で庭周りから部屋の装飾、テーブルsettingを変え、我々に料理と言う事がただ食べるだけでなく、生活を楽しみ、心を豊かにすることだという事を言葉でなく、形でさりげなく教えてくれる。その上自らも若さを保ち、美しくいることを心掛けているから、すごい!!
更に、探究心旺盛で勉強熱心で頭が下がる。(これこそ若さの秘訣?)
「先生、これおいしそうですね?」と言うと「おいしいのよ!」と笑顔できっぱり答える。
そうか、私などは、人に「おいしそうね」と言われると「だと、いいけど――――?」としか言えないのが本心だ。この誇りと自信を裏付ける経験と実績は、ピアノ教師としても見習いたいものだ。
最近、ビデオで「料理人ヴァテール」という映画を見た。ルイ14世をもてなす大饗宴を主催する料理人の話だ。
そのヴァテールが料理を盛りつけながら言う言葉が印象的で心に残った。
「調和と対比」、美はこの2つから生まれ出る。
その組み合わせいかんで美と醜が決まる。それを知ることが芸術家の第一歩だ。
料理も絵画や音楽同様、芸術の1つだと確信する一言だった。 |
|
|
|
| 体育の日だった。
我々ピアノ教師は、休日ともなると、学生が朝からレッスンに来られるので、一般の人が休みとなる夏休みや、休日,祭日は逆に大忙し。だから因果な職業である。
自分は納得してレッスンを入れているからいいようなものの、家族にとってはいい迷惑だ!!
申し訳ないと思いつつ20年経過してしまった。(この場を借り家族の皆さんごめんなさい。)
体育の日と言えば運動会だ。町内の運動会に息子と参加したのは、大昔の幻の様だ!!
今はと言えば、秋から冬にかけてのコンクールの準備だから、こっちも目的こそ違うが、運動会に似た様相を呈している。
大体「コンペティション」を訳すると"競争"と辞書にあるではないか!
この間日本における現在の教育の競争社会のあり方についても国会で野党が代表質問をしていたくらいだから、社会問題である。
今の子は、学校、塾でも成績の順位を貼り出され、唯一"情操教育"でもと始めたピアノでは、コンクールに参加して、また点数を付けられるのだからたまったものではない。
しかし、この間、ふと読んだ新聞のコラムが気になり、取っておいたのを思い出したので、ここで紹介しよう。
皆さんはどう思われますか?
日本経済新聞10月2日 「明日への話題より」 サントリー相談役 津田 和明氏
運動会シーズンに思う
パリで開催された世界陸上選手権の二百メートル競走で末続慎吾選手が三位に入賞した。
オリンピック、世界陸上を通じて日本人が獲得した短距離レース初のメダルである。
ご本人は、成田空港へ凱旋した時、集まっている報道陣の数の多さを見て、自分の快挙に改めて気づいたようだ。記者から感想を聞かれて、「子供の頃、運動会の日だけは活躍できた。皆から誉められるのが励みになって、将来はオリンピックに出場できるような選手になりたいと思った」と話していた。爽やかな人柄だ。
私は小学生の頃、体力はあるのに、花形種目である短距離競走になると勝てず、運動会は苦手だった。中学二年の時、男子のみの旧制中学は、学制改革で男女共学に変わった。見栄を張りたい年頃だ。惨敗するのは辛い。運動会が近づくと、裏の原っぱでスタートダッシュの練習をひそかに繰り返した。半ば諦めていたのに、努力すれば速くなるものだ。これで運動会嫌いも少しは解消した。
近年、小学校や中学校の運動会で、徒競走の順位をつける事を止めているところがある。
「順位をつけるのは差別である」と言うのが理由らしい。一部の小学校では、ゴールの直前でもう一度、横一列に並ばせてからゴールインさせていた。このような運動会から、末続選手のようなオリンピック選手が育つであろうか。学業についても全く同じことが言える。
挑戦する機会は平等であるべきだが、努力や才能によって、結果に差が出ることは当然である。負けてもその悔しさをバネにして努力することが大切だ。出る杭はどんどん伸ばしたい。 |
|
|
|
| 芸術の秋到来だ!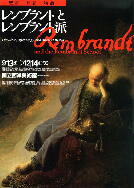
今日は東京レッスンの帰り、上野の国立美術館で
「レンブラントとレンブラント派」を見てきた。
私は元々絵が好きで子供の頃は「絵描き」志望だったが「絵は、天才でもないと1人前になれないの」との母の一言で一笑に伏され、絵への夢は断念させられたが、しかし油絵に対する憧憬は,募る一方。
音大に通いながら、ついには画家の伯父の下で、念願のキャンバスを前に絵筆を持つ夢を実現させた。
しかし、その後伯父の死、結婚、転勤で私の油絵道具は物置深く、しまわれたままだ。
絵とのつながりは、今となっては美術展へせっせと足を運ぶくらいの希薄な関係になってしまった。
そもそも、レンブラントとの出会いは子供の頃の書棚の美術絵集だった。私の母はその昔、大層教育ママで子供には一切テレビというものを見せてくれなかったので、娯楽は「本」でしかなかった。
読書というものが我が家の習慣だった。しかし、不真面目な私は活字を追いかけるのが苦痛なので、いつも暇さえあれば美術絵集を見ていた。
そのうち書棚の何番目の美術の本の何ページ目に何の絵があるか?まで覚え込んでいる内に、持ち前の好奇心からか、絵の背後の物語を知りたくてたまらなくなった。
「一体この絵の主人公ってどんな人?」「神話の神様の役割って?」「天使の種類は?」「聖人の特徴は?」等々疑問は数え上げたらきりがない。好奇心と想像力を膨らませた少女時代を過ごした。
その後、大学で美術史を専攻し、つい最近では少女時代の疑問を解くべく「絵画に見るギリシャ神話」なる講義を聴きに横浜の朝日カルチャーセンターに数ヶ月、通ったりもした。
おかげでギリシャ神話には精通したせいか、絵における神話の謎はかなり解けた。
しかし旧約聖書、新約聖書は、未踏だ!これを知らないとレンブラントは、まだまだ解読不可能。西欧の文化は音楽も同様だが、宗教とは切っても切れない関係にある。
聖書は西欧文化の思想哲学の根源だから奥が深いのだ!
今回のレンブラント展では、レンブラントとその弟子達の作品に焦点が当たっていた。
同じ題材を巨匠であるレンブラントとその弟子達が描いているのだが、その違いには驚いた。
技術は元よりだが人物の表情の深い心理描写が描かれているレンブラントに対して、弟子達のそれはあまりに浅薄なのだ。どの絵を見てもそうなのだ。その写実性は裸婦においてなどは目をそむけたくなる程リアルなのだ。
人間の苦悩や当惑、困惑した表情、深く刻まれた皺、静脈の浮き上がった手足。これら人間の表情には神話や聖書を超えた説得力が有るのだが、解説書によると、レンブラントは実生活の似た体験を神話や聖書の主人公に重ね合わせていたのではないか?ということなのだそうだ。
なるほど、そのただならぬ写実性が、真に迫っていたことがうなずける。
絵は、何百枚も見ているとボーッと見過ごす事があるが、本物と言われる前では、足が自然と止まる。
多分、絵の中から画家の魂が問い掛けて訴えてくる絵とそうではない絵があるのだろう。
言うまでも無く音楽もそうだ!!これは、言葉や理屈を超えた芸術の共通点なのだろう。
余談だが、興味深かったのはレンブラントの生きた17世紀、当時流行したバニタスという静物画の特徴だ。
バロック絵画に良く出てくる小物「砂時計、どくろ、鏡、楽器」これらは、人生のはかなさの象徴である富や名声のむなしさを強調するものだというのだが...。
どくろ、砂時計は分かるが、何故楽器なんだ?と疑問を持ちながら上野の森を後にした。
|
|
|
|
| 浜松アクト大ホールにて、マルタ・アルゲリッチ 協演による、 協演による、
「ミラノジュゼッペ・ヴェルティ交響楽団」を聴いた。
勿論お目当ては生アルゲリッチの演奏だった。
彼女のドタキャンは有名なのでS席11,000円をゲットして当日までヒヤヒヤしていたが、無事に聴くことが出来た。
アルゲリッチの演奏の前にシェーンベルクの「ハープと弦楽のためのノットゥルノ」を聴いた。ノットゥルノというのは、夜想曲だが、シェーンベルクの言い知れぬ甘美なハーモニーとメロディー、寒気のするようなヴァイオリンの音色に酔いしれ、つくづく音楽に関わる仕事をしていて幸せだと思った。それ程どんな録音CDをもっても、生オーケストラの迫力に勝る感動は無いのだ。
さて、問題のアルゲリッチは、Beethovenピアノ協奏曲第1番ハ長調だった。
この初期の作品は、ハイドン,モーツァルトの影響を受けているのだろう。若々しく、難聴の苦悩から程遠い明るい覇気に満ちた作品だった。アルゲリッチの演奏はどうだったかというと、主張過ぎず、誇張過ぎず、自然体でオーケストラと一体化し、溶け込み、馴染んでしまって、しばし、それがピアノという楽器ではなく、弦であり、ハープであったりするのだ。職業柄ピアノというパートを聞くと、楽譜が目の前に見え隠れし難しいパートに緊張してしまう自分がいるのに、アルゲリッチは全くそれを感じさせない。
ただ、ベートーヴェンの精神性の世界にいることだけに没頭させてくれた。
だから心に残ったのはアルゲリッチでなく、ベートーヴェンという偉大な作曲家の作品から受ける感動だけだったから不思議だった。今まで味わったことの無い体験だった。
頂点を極め、成熟した世界的なピアニストともなると作曲家と一体化する術を持っているのだろうか?ピアノを奏でていながら、無心忘我の境地なのだ。
兎に角、ベートーヴェンを聞いたという感動が純粋に残った。
もう1つ、3楽章のロンド・アレグロ・スケルツァンドを聴いていて感じたことなのだが、西欧の音楽の躍動感は、「乗馬とダンス」が基本なのだということを改めて強く感じた。
ホルンの角笛の響きに貴族の趣味である狩猟の様子もまぶたに浮かぶ。農耕民族である日本人には無い、この躍動感とダンスの習慣は、2拍子、3拍子と言う形で、4拍子民族の日本人に立ちはだかるではないか?
所詮外国人がどんなに学んでも歌舞伎の「睨み」を演じた所でどこか奇妙なのと同様に日本人は西欧人の「ルバート」や「リズム感」を真に理解できてはいないかもしれないと思うとショックである。
さて、私は音楽を聴く時、作曲家がどんな時、どんな気持ちで、どんな景色を見ながら、どんな感情を膨らませ、心の中にその音楽を迎え入れ、そしてそれを羽ペンにインクをくぐらせ、五線紙上に音譜にしていた瞬間を想像し、聞くのが大好きである。
こんな聴き方をしているのは私だけだろうか?
危うげなオーケストラを聴いていると、その想像力が演奏の不安によって遮られ、作曲家の魂と交信不能になってしまう。
だから、やはり音楽は常に本物でなければならないというのが私の素直な心情なのだが...。
今日の演目最後のブラームスの交響曲第1番はそういう意味では、「管」が今ひとつで残念だった。
今日は、やはり何と言ってもアルゲリッチが最高だった。
|
|
|