| 発表会の準備、引っ越し、4月からの新しい学院のスタート準備やらで、何が何だか分からない状態なのに、今週は暇さえあれば本を読んでいた。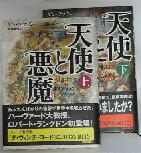
ダヴィンチ・コードが面白いと言ったら、同じ著者(ダン・ブラウン)の作品でダヴィンチ・コードより以前に書かれたもので、(その方が傑作だという人もいるそうなのだが)分厚い2冊の上下巻「天使と悪魔」を借りたのだが、すっかりこれにはまってしまっていた。
この本は、たった1日の出来事を、この2冊の上下巻で、まるでサスペンスタッチで読む者をぐいぐい引っ張っていた。
ダヴィンチ・コードは、ルーヴル美術館とレオナルド・ダヴィンチの作品に言及していたのに対し、こちらはローマ・バチカンが舞台、イタリアである。
科学と宗教の対立という、深遠なテーマを扱っている、スケールの大きな作品である。
ダン・ブラウンの作品の魅力は、膨大な量のうんちくが満載されている事である。
美術史、建築、地理、歴史の専門的な知識と学術的な調査、考証が綿密で、読みながら、さながらバチカンやローマを歴史案内されている様な気がする。
これはダヴィンチ・コードでも同様だったが、単なるサスペンスではないから、読むだけで知的・好奇心が大満足なのである。
現実逃避、忙しく旅行の出来ない私には、うってつけである。
という訳で、歴史とか美術とかが大好きな私は、無我夢中という訳なのだ.....。
しかし、読むのも寝る前、睡魔との闘いで、「ファー」とし睡魔に襲われては、思い直して本にフォーカス、いや寝ちゃ駄目、寝ちゃ駄目、暫くすると「ファー」としては、又フォーカスの連続だから時間がかかった。
それでも電車や新幹線の移動、そして最後の晩は、半分徹夜して読んでいた。
ダヴィンチ・コードより少し難易度が高いが、ずっと面白い様に思った。
この作品が面白く感動的だったのは、物語の筋立てとスピード感だけではない、人間にとって"科学と宗教、どちらが大切か?"という事を扱っていていた事が、興味深かった。
ローマ教皇の侍従である若き司祭が、「人類にもたらされた科学の発展は、人類を果たして幸せにしたであろうか?」と演説する場面は圧巻だった。
一方、バチカンの衛兵が、プライベートでその若き司祭に尋ねる場面である。
「人は何故信仰を厚くしたところで、怪我や病気はおろか、テロなど悲惨な事故や事件などに見回らなければならないのか?」と尋ねるシーンである。究極的には神を信じるよりもSECOM(自己防衛)ではないかという訳である。
司祭は語る。
「あなたにはお子さんはいますか?」
「お子さんが、スケートボードをしようとしたら許可しますか?」
「はい!気を付けて乗る様にと。」
「それでは息子さんの後ろに付きまとって転ばない様、怪我をしない様、ずっと付きっきりで離れませんか?」
「いいえ」
「では転んで怪我をしたらどうしますか?」
「これからは気を付ける様にと」
「子供は転ぶ事によって、どうしたら次に未然に事故を防ぐか?を考えるのです。それが大切な事です。」
このシーンは、これで終わりである。最初はこれが信仰と人間の不運と、どういう関係があるか分からなかったが、次第に読み進むうちに分かってきた。
そのキーワードは、司祭が「科学は、いやす事も出来るが、殺す事も出来る。それは科学を操る人間の心次第なのです。私は、人間の心のほうに興味があります。」というくだりだった。
かわいい子供が、色々な意味で怪我をしない様に、あらゆる事を未然に防ぐべく、科学の力を総動員して守ってみたら、果たして子供は強い子に育つだろうか?
勉強だけ出来ても、心優しい子に育つだろうか?
親の我々も、どんなに辛い事があっても、困難と戦える様な強い意志が、いつだって人生においては、試されているのである。
戦争やテロが無意味な破壊である事に気づく事は、人間の使命であり、科学の発展をどう利用し、どう役立て、人間が幸せに生きるべきか?
"人はどうあるべきか?"の根源(人の心のあり方)を問う事こそ宗教なのだろう。
科学を利用するのは人間の心だからだ。
そんな事を考えていたら、この本はとても有意義な事を教えてくれていて、単なるサスペンス本ではなかった。
というのも、先日ある雑誌で、大江健三郎と小沢征良との対談を読んだのだが、人間は数学的、科学的なものを超えた能力を持っているらしい。
例えば、コンピューターと人間が、将棋やチェスの試合をすると、理論的にはコンピューターが勝つに決まっているのに、人間が勝つ場合がある。
その直感的な人間の優れた力をどうして創り出せるかというと、"注意深くある"という事なのだそうだ。
その特徴は、常に方向性を持っているという事で、養われるのだそうだそうだ。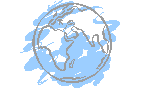
ある方向を予め選択している人間は、注意深いのだそうだ。
理科の時間に出てくる"ベクトル"という言葉は、質量と方向を示すもの。方向がなければ、重さがあるものの運動も"力"にはならない。
心の動きでいうと、「願う」のは、ある方向を持って願う事だというのだ。
それと同時に、重要な事は、いったんやり始めた事は、持続するという事なのだそうで、エネルギーの働きで、方向性と共に重要なのは、ある運動がどれくらい持続するかという事なのだそうだ。
持続する事、方向性をもつ事、これは人間の行動の原則なのだという。
宗教が、人間の人間としての在り方を求めていく哲学とすれば、科学はその人間が如何に利用するかで、発展も後退も破滅も自在である。
そして人間は、科学を超える能力を持っている。それは全てに注意深く、目も耳も頭も常にフル回転している事。それは方向性を持ち、目的意識を持って生きる事。そして常にそれを持続させる事なのだそうだ。
音楽は、その一番、人間が人間らしくある部分に関わっている事。そして教育は、子供達に常に目的意識を持たせ、努力させ、それを持続させていく事なのだ。
注意深く自分や周りを見つめられる人間性を養う事。教育の意味は大きいと思う。
今週は、大江健三郎とこの小説が、しっかり結びつき、自分自身に生き方を改めて考えさせてくれた。 |
|
|
|
| 3月は本当に忙しい。
普段から目が回るように暮らしているが、さらに高速コマになっている。
4月の発表会もあるので、事務能力に欠ける私は、何だか雑用に日々追われながら、一日一日優先順位を少しずつ付けながらこなしているという感じである。
実は3月末に引越しである。
自宅は築20年以上で、増改築を3・4回しては何とかレッスン室と自宅を共用していたものの、プライベートがかなり侵略され、いささか無理が生じ始めていた。
これを契機に別の場所に家を建て直し、小さなマイホールを兼ねたレッスン室を増やし、プライベートを確保したという訳である。
レッスン室を増やしたという事で、教室の卒業生達に手伝ってもらい、小さい子供達を育てる事にこれからは情熱を傾け、自分の後継者を育てていこうと思っている。
メリットのひとつに、コンクールのたびにいろいろなホールを借り歩くのもしなくてよくなるのだから何より嬉しい。
という訳で、秋から家を建築中だったが、この春完成である。
三好ピアノ教室は、「ミューズ音楽院」と名前を改め、藤枝の「緑の丘」で再出発である。
ミューズとは、音楽の神様の事だ。いつもこの神様に守られている様に、勝手に自分なりに自己暗示をかけて頑張ってきたのと、それに三好⇒ミューズなんて、語呂合わせも良いので、私としてはお気に入りである。(Informationに詳しく載っています。)
3月からは2歳児から生徒を募集している。
1歳半の子供達を教える事の出来る、頼もしい私の卒業生でもあるベテランの先生。
絶対音感の勉強をし、資格を取った真面目で誠実な心優しい先生を迎えて、これから新しく再スタートなのである。
一人で勝手気ままにやってきたので、これからはいろいろと大変な事もあるだろうが、理想の音楽教育を自分の愛し育てた生徒達とやっていく事が出来るのだから、夢と希望でいっぱいである。
その前に引越しである。
考えただけで大変なので、あまり考えないようにしてはいるものの、20年以上も住んでいるとゴミと不用品の山である。
これをどうやって片付けるかを考えると気分が悪くなるので、やめている...。
理想を追うのも大変である。 |
|
|
|
| 春は名のみの風の寒さよ。
今週は"三寒四温"の名の如く、氷雨の多い寒い日が続いた。
巷が受験シーズン真っ盛りなら、はっきりしない天気がかえって救いでもある。
何故って、春爛漫になってしまうと、まだ行き先の決まらない受験生達がなんだか季節に取り残され、可哀想である。
今頃、皆不安な毎日を過ごしているに違いないし、梅の花も目に入らないだろう。
うちの教室にも、4月1日の発表会目前にして、受験が終わるまで休んでいる子がいる。
ピアノを一生懸命頑張っている子だっただけに、心の中で無事第一志望に受かって、笑顔でまたピアノに向かってくれる姿を願いながら待っている。
というわけで、4月1日は恒例の発表会である。
なのに、プログラムもまだ作っていない。実は引越しもある。(この事については、またの機会に触れることにする)
いつもストレスの海で泳いでいる私だが、この所あまりに波がたくさん押し寄せてくるので、さすがにパニクリだしている。
慌てない、慌てない、一つ一つ片付けなくては!と言い聞かせている所へ、ピティナの課題曲が出てしまった。
コンペはこの間終わったばかりなのに、もうコンペの季節到来ということなのだ。(汗) |
|
|