| ピティナ予選も終盤に近づいている。
今年は、静岡は6月初旬だったので、本当に早くから大変だった。
6月末から、どの子も本来の力を発揮したが、初旬の審査の厳しさには、驚くばかりだった。
友人の全国大会常連の先生方も、予選で苦労していたから、年々厳しい予選はうちだけではないようだ。
それにつけても、審査の講評、点数のばらつきが気になる事がある。
それに対し、色々な回りから不信の声が聞こえるが、私は正直いってあまり気にならない。
20年も同じ事をしていると、棄てる神あれば、拾う神あり、というのが本音だからだ。
かといって、お気軽に構えているわけではない。絶対大丈夫と太鼓判の全国狙いの子が、予選を次点で落ちてきて、「いつも通り弾いた。」と言われると、目を白黒させ、「何で、ウッソー」と不安になるのは、人間として当然の心境だろう。
親御さんの落胆ぶりは、"先生に言われた通り弾いたのに?"という視線を浴びる様で、辛いものがあるが、ここはそれ、20年の経験の開き直りが物を言う。
"色々な審査の基準があるのだから"という事をうんと話して聞かせて安心させる。
まず、その基準とはである。行き着く所は、審査員も生身の人間だという事で、レベルの高い予選では、審査員も呑気に聴いている訳にはいかない。
どの子も、どの子も素晴らしい指導者に、隅々まで良く教えられてくる。これが何人も続くのである。ふと、何も無い、飾り気の無い、教えられてないシンプルな美しさ、素直さ、素朴さに引かれる事すらある。
(フランス料理のコース料理ばかり食べていたら、白飯に梅干が懐かしくなる心境だ。)
逆に、あまりにどの子もシンプルだと、細部まで行き届いた演奏が刺激的でもある。
弾き順、選曲、子供のコンディション、ホールとの相性。要因は様々である。
大きな音で、強すぎる子は、小さいホールでは、叩いたと書かれ、審査員が後方でチェックしている広い会場では、小さな音の子供はそれだけで不利である。
手首まで見えてしまう前列では、基礎が見えてしまうが、後方ではそこまで見えないから、結構基礎のない子にとっては、ラッキーな時もある。
同じ曲が続いて、うんざりの時に、違う曲が入ると、とても新鮮に映る事だってある。書き出したら、きりがない。
最近長年審査をする立場で、同じ審査員の先生と交流を持って分かった事だが、普段あまり小さい子供の指導に携わっていない立場の先生方は、楽譜上の細かい事には、あまり触れず、大らかに音楽をPUREに聴いている事だ。
これはとても怖い事だが、本当は大切な事だと思っている。
我々、現場の先生は、あまり細部に目が行き届きすぎ、研究し尽くすあまり、子供本来の子供らしさを失い、作りすぎてしまうことが多い。
"木を見て山を見ず"状態に陥りやすい。
数ヶ月も16小節や32小節に関わっていれば、当然といえば、当然だろう。
だから、作曲家や、大学生相手の先生方は、小さい子供の評価の観点が違うように思う。
要は、才能に目を向けている気がする。(一概には言えないが、その傾向があるのではないだろうか?)
音楽そのものの創りより、音色や音楽の自然さに評価が高いかもしれない。
逆に、現場で小さい子供達と日々悪戦苦闘している我々は、小さい子供がここまで、細部まで、気を配り、練習を重ねた事が、如何に大変だったか、如何に作られすぎと言われ様が、作る事自体、親や指導者が、やる気の無い子供達を引っ張り、日夜苦労をして、それを作ってきたか?分かる由縁。そこに評価を置く。勿論、"もう少し自然!"にとは書くが、その努力に7.5はあり得ないものだ。
人間だから、好みがあって当然だけれど、好みで努力まで評価されないのは、悲しすぎるし、残念だ。
しかし人それぞれだから、何とも言いようが無い。
あり得ないミスをしても、生き残ることもある。それは、審査員の判定ミスだろうか?ノーである。
ミスだけで、音楽を評価するコンクールなら、空恐ろしいコンクールである。逆に完璧に弾いたから、9.0なのだろうか?
完璧とは、一体何であろうか?
審査員の先生によって、8.5が最高点だったり、8.8だったり、8.3だったりするのだ。
私は、審査の基準をコーヒーの自動販売機だと思う。
あれは本当に大変である。ブラック、アメリカン、キリマンジャロ、モカ、アイスコーヒー、アイスカフェオレ・・・etc.砂糖入り、砂糖無し、クリーム入り、クリーム無し。各々クリーム増量、砂糖増量、甘さ控えめ。何が何だか、これだけ組み合わせがある中で誰からも、嫌われず、逆に好かれ、そして誰もが認める音楽を作る事の難しさである。
しかしなのである、我々審査員は、皆色々な立場も、好みも違うが、お互いを尊敬し合っているものだ。
というのも、コンクールでの一位、2位、3位というのは、ほとんど全員が一緒で、揺るがないものだからだ!これは本当に不思議である。
感動というものは、なんだろう?
電気みたいなものかもしれない。一瞬にしてビビッと、全員をしびれさせる。それは、音楽の一瞬の間だったり、集中力であったり、美しく透き通った音色であったり、きっとそれは、私は、その子がピアノを弾いている間、消える事だと思っている。
それが、シューマンやショパンやバッハが時空を超え、そこに子供の体を通して、現れた瞬間なのかもしれないと思う。
そこには、ミスもテクニックの不安も作られたものも、すべてを超えている瞬間かもしれない。
指導者の陰も、本人の賞に対するこだわりも無い、何かが訴えてくる。
それがプロだけに分かる本物を見極める力ではないかな?と思う。
なんだろう?オーラみたいな物を発しているのだ。
それが魂を通して訴えかけてくる。誰にでも、それは出来ないものかもと思うと、そんなことは無い。集中力だろうか?信念だろうか?
それがテクニックの不安や、メンタルな面の不安定さで、遮られ、出きれないとオーラはおのずと発光しない。
あの曲のあの部分はフォルテが有利だ、ピアノが有利だ、ゆっくりだと受かって、あのテンポでは駄目だとか、曲想が当たった、当たらない。ひいては、あの曲は損だ、得だ!!と騒ぐのを聞くと、とても残念だし、ナンセンスだと思う。
曲想も、強弱も、テンポも、ペダルも、その作曲家の魂を引き出す手段であって、方法では無いのだ。
そうでなければ、ピアノの表現など皆一緒になる筈だ。
色々なピアニストの、色々な演奏があり、皆好きな演奏家がいて、当然だ。
それが芸術の世界の良い所で、答えがいくつもある。個性の競い合い、ぶつかり合いだからだ。
その一方、オーラを発光出来る演奏者の後に来る順位の子供達は、審査員が音楽のどこに評価観点を持つか?で評価が分かれるということだ。
その審査員が、一番嫌う観点(地雷)に触れてしまったら、点が大きく下がるし、好きな観点に触れたら(ツボにはまる)点が高い。
これが審査員との相性だから、運という訳である。
以前"マリア・J・ピリシュ"がテレビで言っていた。
「コンクールの勝敗に、あまりこだわると、大切なものを見失います。」と
コンクールは、利用するものであって、その評価が絶対では無い事だ!
この事を心に刻んでおけば、一喜一憂して泣いたり、わめいたりせず、結果を前向きに受け止め、これからも頑張れる気がする。 |
|
|
|
| 子供のやる気の問題は誰もが抱えている問題です。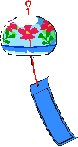
「お宅のお子さんは、やれば出来るのに」と言う言葉は、誰しもがピアノのみならず、1度は耳にした言葉だと思います。
お問い合わせのお子さんは、小学校6年生ということで、とてもこれからが不安です。
というのも早い子で、反抗期は小学5年生から6年生。猛烈な反抗期が、中1から中3までです。
中3後期になると、受験の目標が定まるせいか、少し落ち着きますが、一番すごいのは中1,2の女の子で、男の子は少し遅いですが、高校生になると、「メシ、風呂」以外口もきいてくれません。
ピアノは、親子一体型が殆どです。そうでもないと毎日の練習を2時間から3時間、親の言いなりになってやれないからです。
その反発は、粘着度が高いほど激しく、親には辛いものがあります。
中には小学1年〜2年生で反抗期のあるお子さんが稀にいますが、あまり口うるさい親に四六時中、かみがみ言われていると、モラトリアム(無気力)人間になり、何事も真剣にやらなくなります。
これは完璧主義の母親に育てられている子が多いようです。
多分、何をやっても母親の希望通りには出来ない自分を変えて、真剣にやって傷つくより、やる気をなくして逃げることによって、自分を守っているのかもしれません。
同じ母親に育てられながら、姉妹・兄弟ではそれぞれ違うので、一概には言えないのですが、子供の性格を見極めて、やる気のなさがどこに起因しているかを見つけてあげないといけません。
ご指摘のお子さん(小学6年生の女子)ですが、お母様がピアノの先生ということは、子供にとっては良し悪しです。
というのも、我々はピアノに関してあまりに知識がありすぎる訳です。
要は、ゴールが見えているのだけど、そのゴールに到達するのには何が必要で、どんな練習が有効であるかが分かり過ぎてしまう。
楽譜の正確な読み方、楽典的配慮、ソルフェージュの重要性、テクニックの重要性など、子供に面白おかしく、優しく、楽しみながら教えてくれる先生より、高度な事を深く教えてくれる先生を、自ずと選んでしまっているところなど、数え上げたら、その功罪はキリがありません。
私の例をとっても、一人息子に当初から立派な先生を選択しすぎ、先生にピアノの先生の子供がこんなこともしていないと言われてはいけない、レッスンで先生に負担をかけてはいけないという思いが強くて、練習させ、教え込み過ぎ、子供をピアノ嫌いにしてしまいました。
今から思えば、楽しいお姉さん先生で、遊ばせながらピアノを続けていって、本人がその気になった時に、立派な先生に変えてあげれば良かったと今でも悔やまれるのです。
私が以前一度、自身が習っていた大先生、その方はピアニストで、日本でも指折りの方ですが、生徒を連れていったら、「あなたも習わないと教えられません」と言われ、何年か脱力のテクニックのみを習いにレッスンに通った事がありました。
その大先生がおっしゃったことが印象的でした。
「やっぱり大切なのは、テクニックです。中でも脱力のテクニックは、無いと所詮表現力があっても、伸び悩んでしまいます。美しい音も響きのある音も出せません。
しかし私にはとても残念な事があります。
お母様は熱心なピアノの先生で、小さい頃からお嬢さんをお預かりしていたのに、私はもう1〜10まで、私の学んだすべてのテクニックの基本を教え込み、中学生になり、さあ何でも弾けるわよ。
コンクールも受けさせようという段階になったら、あっさり"ピアノはもうイヤ"とやめてしまい、本当に残念でたまらなかったわ。」
「あなたの生徒は、基本が、まだまだだけど、大きくなってもやる気があっていいわね」と言われた事でした。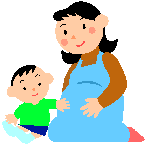
私は私で、テクニックで悩んではいたので、そんなお嬢さんのテクニックの話を聞くと勿体なくて、生唾ものでした。
大先生も本当に惜しかったとおっしゃっていました。
私はそれまで、結構いい加減に、子供に自由にピアノを教えてきました。テクニックもやるけれどあまり口うるさくは言いたくない方です。
テクニックに口うるさくなりすぎると、マルもちっとも貰えない。
子供は達成感がないから、うんざりして、いつまでもいつまでも同じ曲をやらされていたら、飽きてきてうまくなるどころか下手になってしまい、ついにはやる気を失っていきます。
かといって、うるさくテクニックを言及しなければ、いつかは頭打ちなのです。
そこで私は、コンクールを利用することにしたのです。
コンクールでは、その子の弱い部分がはっきり出てきます。レッスン室では優等生だった子が意外に表現力の薄い、アピール性のない子だったり、指先が弱く音がはっきり出なくなったり、脱力が出来ず、手首が硬くて、音が伸びなかったり、親と私と子供含め弱点を見極めることが出来ました。
子供は、勝ち負けには敏感ですから、「ではどうしたら次の戦いで勝てるか?」を考え、先生のテクニック補強作戦にも乗ってくる訳です。
ご指摘のお母さんは、ハノンを全調、インベンションを全曲暗譜して、転調という作業を、親やピアノの先生の意図を汲まず、ただ作業として、素直に受け入れているだけなので、今は決して、それは彼女の身につく事は無いのではないでしょうか??
(でもいつかは、役に立つのですが)
それも素直にやっているだけ、素晴らしいですが、"魔の反抗期"が来たら、それもやってくれなくなる時が来るかもしれません。
いかに本人にそれが必要か?を考える時、子供としてでは無く、我々大人に置き換えてみてください。
我々は,例えば5Kg痩せたい!と漠然と考えますが,それには大変な努力と忍耐が必要です。
しかし、着たい洋服を目の前に吊るすと、それに向けて日夜努力を繰り返す訳です。
しかし、目標のない人に、ただ食べるなと言っても無理でしょう。
「あなたやる気があるの?将来何になりたいの?"ピアニスト?"それなら、これをコツコツやらなければいけない!」と言われても、そんな大きな目標すぎて、漠然としすぎて、努力は出来ないものです。
私は例え、小さいコンクールでも、出して達成感を与えつつ、本人に努力の結果が少しずつ表れ、毎日の努力が実っているねと実感を持たせながら、そしてまた、足りなかったら、"ハノンの練習の仕方を変えてみようか?"と本人に認識させる事です。
達成感や、自信をつけたら、やる気も起きてくるし、逆に駄目だったら、"これではいけない"とやる気が目覚めるかもしれないのです。
「コンクールで負けてもいいもん」と言われちゃうと困りますが、そんな事を言う子供ほど、勝敗を気にしているものです。
かつて、その大先生が、「今の子はコンクール、コンクールとコンクールが無ければ、練習しないけれど、私なんか戦時中、灯火管制下でもピアノを弾きましたわ」とおっしゃいました。
しかし、今の子供は塾や学校の宿題に追われ、テレビはおろか、休日もない状況です。まして、たまの暇な日は、遊びやゲームやらパソコンやら、いっぱいあり、たまごっちにえさもあげなくてはいけないのです。
とても、朝から晩まで好きにピアノを弾く状況にないのです。
この多様化した時代に、ピアノをうまくなって欲しいと思ったら、やはり親や指導者が、1枚も2枚も上手になり、子供をリードするしかないと思うのです。
子供自身が、本当に痩せて、このドレスを着たいと思うようにならなければ、減量は無理なんです。その苦しいダイエットは、永久に続くと考えたら、いつか爆発してしまうでしょう。
1日も早く、本人に達成感を与えてあげる事。今、自分のやっている辛い作業が、具体的に何に繋がっているのか、分からせてあげる事ではないでしょうか?
また"コンクールの達成感・やる気"と"弱点見直し・出直しやる気"とは 別に、それとはまだ関係ない段階の子供達には、工夫が要ると思います。 別に、それとはまだ関係ない段階の子供達には、工夫が要ると思います。
例えば、幼稚園や小学校低学年の子供には、その子が一番嬉しいと感じるものをご褒美にしてあげること。
私の友人でピティナでは有名なY先生は、コンチェルトで出会った生徒の楽譜に、プクプクシールが所狭しと貼ってあり、その子はそのシールを撫でながら、にんまりしていました。
「ハ・ハーン、この子はこのシール目当てにピアノをやってんだな!!」、なかなかやるなY先生。
今は、桐朋の高3になった優秀だったSちゃんは、小学校5年生〜6年生の時も、全国大会に行けたら、ぬいぐるみが買って貰えると頑張っていました。
ものにつられて、ピアノを弾くなんざ、邪道と思いきや、人間誰しも、大人だってエサ無しに頑張れないものです。
その子が一番喜ぶ事で、釣るのも手ではないでしょうか?
本当にその子が、自分の人生にピアノをどう位置付けるか?までは、邪道も多いに有効だと思うのです。
要は等身大の子供の心を掴む事ではないでしょうか?
高学年から、弾きたかった曲を、力がないからと取り上げず、失敗しても良いではないか?
本人がやりたい曲をやらせてあげる事も、大切な気がする。やる気を育てたら、後はこっちのものだからだ。本当にやる気なんてひょんなことで育つし、エッとびっくりするような大人の言動で失う事もある。
指導者も親も、本当に子供からか学ぶことが多い。
それにつけ、大人は知らない内に、子供の時の童心を忘れてしまったのだと思う。
もっと子供の背丈になって、何事も見つめてあげられたら、やる気も育つような気がするのです。 |
|
|
|
| ブロードウエイで有名な舞台ミュージカル"オペラ座 の怪人"だが、ストーリーはミュージカルではなく、多分子供の頃、映画として見た事があるので中身は大体分かっていた。 の怪人"だが、ストーリーはミュージカルではなく、多分子供の頃、映画として見た事があるので中身は大体分かっていた。
地下牢に住む怪人が、美しく若きオペラ歌手の卵に恋する話で、私の中では"ジキル博士とハイド氏"、はたまた"美女と野獣"の仲間の様なストーリーとして、把握していたから、ミュージカルとして甦った"オペラ座の怪人"はとても新鮮に映った。
とにかく音楽が素晴らしい。それに加え"歌詞"だ。
画面いっぱいに出てくる字幕の歌詞は、まさに詩そのものだ。
中国には漢詩、日本には俳句・短歌があるが、西洋の文化は言葉がストレートで照れる程だが、西欧人があの容姿で語ると、如何にも自然だから不思議だ。
理屈っぽいとも言うのか、沈黙を美徳とする日本人に対し、雄弁なのがヨーロッパ人の本質か?まあ、ミュージカルだからなのだが、歌詞がロマンチックだ。
<ポイント・オブ・ノーリターンの一節>
あとどのくらい待てばいいの
私たちが結ばれて――
熱く燃える血が全身を駆け巡って――
眠ってたつぼみが開くまでに?
情熱の炎に――
私たちが燃え尽きるのはいつ?
ここに来たからには
後戻りは出来ない
何も考えずに――
夢に身をゆだねるのだ
どんな熱い炎が魂を包み込むのか
どんな欲望がそのドアを開くのか
どんな甘い誘惑が
我々を待ち受けているのか
ここに来たからには
後戻りは出来ぬ
見ている最中、一語一句読みきった。多分、訳詩者が泣いて喜ぶだろう!
(訳詩の戸田奈津子様、いつもあなたのファンです〜)
しかし、こんな事を直接言われたらキザ!の一言だろうが、ヨーロッパの詩には、実際にこういう言い回しが多い。
愛をささやく恋人が、窓辺で、ギターなどで即興的に恋人を愛でるセレナーデの歌詞も、さもありなんと思うのだ。
日本人は、歌に託し恋情を恋人に送ったが、そこはかとなく自分を木や山や川、鳥や自然に喩え、相手の教養や知性をそそる。
それも文化だが、面映く、奥ゆかしい。あなたはどちらが好きだろうか?
しかし、今は"オペラ座の怪人"だ。非現実的で、ロマンチックで、壮大な詩的な表現こそファンタジーだ。その上、歌詞に加え、映像が素晴らしい。
その舞台芸術は、衣装から装置に至るまで、絢爛豪華。19世紀末のパリ・オペラ座の表と裏の部分を余すことなく、溜め息をつくほどの勢いで見せてくれる。
オペラは、本来貴族の娯楽だから、今でもヨーロッパの超一流の劇場は、正装でないと入れない。セレブな人達の空間なのでもある。
そして俳優陣。何と17歳という女優の清楚で品の良い美しさと清らかなソプラノ。
怪人の男らしく、逞しく、強引で悪魔的な魅力と歌声。恋人ラウルのひたむきで優しく、更に包容力に満ちた愛。これぞ理想的な男なのだが、恋人に心を許しながら、怪人の怪しい魅力の虜になる、主人公クリスティーナ!
ラウルも素敵だが、私はやっぱり怪人がいい。多分、女性なら多くは怪人が好きだ ろう。 ろう。
冬ソナのペ様のチュンサンとは、似ても似つかない怪人だが、女はこの手の男に弱い。
その理由は様々だろうが?
安定と平和、それとも刺激とロマンを追い求めるか、時空を超える愛の永遠のテーマかもしれない。
白黒で表現される現実と、カラー映像の過去を比較して(普通なら逆)、カラーが既に過去であるのに対し、この過去が如何に情熱的で、鮮烈で、刺激的な愛であったか?白黒の現実こそ、平和ではあるが、より普通で日常的だったかを比較すれば。
ラウルが、決して愛の勝利者では無かったかもと思わせているわけだ。
「記憶の中のもの程、はるかに鮮やかに現実を上回るものだ」と思うと、過去をカラーにして、現実を白黒にした演出が、心憎いと思うのだ。
Dear ファントム様 From Nobiko Miyoshi
孤独のうちに、クリスティーナを得ることなく、オペラ座の灰と化した貴方様ですが、クリスティーナは、あれからラウルと結婚し、それは、それは幸せな日々を送りました。
子供も儲け、何不自由なく暮らしていましたとさ。
しかし片時も貴方様の事を忘れた事なんぞなかったんでございます。
時折見せる孤独で、遠くを見るような眼差しの先には、いつも貴方様がおりました
仮にも、オペラ座のプリマドンナまで登りつめた彼女が、音楽を棄て、家庭に入り、人も羨む仲睦まじい二人ではありましたが・・・。一体本当に彼女は幸せだったのでしょうか?そんな姿を見るにつけ、夫のラウルは辛い日々でした。
そうです、ラウルは一生ファントム様の亡霊に勝てなかったのでございます。
だからご安心下さいませ
永遠の愛の勝利者は、結局貴方様だったのかもでございます。
音楽の天使ミューズの使いを裏切った報いは、彼女自身が償う結果に終わったものでございます。
〜なんちゃって〜
そうそう、余談ですが、ミュージカルですが、とても英語の勉強になります。ゆっくりきちんと発音されるので、歌詞がとてもクリアです。
文法も分かりやすくて、NOVAに数年通っていた私は、正しい英語の時間が過ごせました。
また、ピアノの先生としては一つ気になったセリフが・・・。
怪人が"音楽の天使"の言う事を信じろという場面である。
音楽を取るか?恋人を取るか?と迫られるクリスティーナが、恋人を選んでしまう事に、怪人は怒りを露わにして、「呪われろ、音楽の天使を裏切った報いを知るが良い!」と怒る。
あふれんばかりの音楽の才能を、ありったけの愛情で育み、育て上げた子供を、安々と恋人に奪われた親の気持ちと重なったのは、私だけの思い込みかしら?
こんな事、結構、音楽の世界にもあるような気がして。いや実際あるんですな、これが・・・。
しかし映画って本当に楽しいですね〜。
映像と音楽、歌詞、STORY、英語の勉強、そして愛について、はたまた恋を取るか才能を伸ばすかを考えさせられ、その上に、刺激とファンタジー、19世紀末の夢の世界にいざなわれました。
度重なるアクシデントにもめげず、巡り合えたスクリーン大画面で、盛りだくさんの収穫に久々の自分の中の大ヒットでした! |
|
|