| 3月21日
春のお彼岸、神奈川の実家でファミリーコンサートに参加した。
私のファミリーとは声楽家の姉とその夫で外国人のヴァイオリニストの義兄、そしてその2人の子供(アントン、アネット)。
地元でピアノの教師と声楽(コーラス)の指導する姉(姉達は双生児)とその2人の子供(高校2年生のS君と現在国立音楽大学に通っている姪っ子のIちゃん)である。
そして私である。私の両親は普通の人だが、音楽というより芸術をこよなく愛する人達で、子供達には勉強より芸術に優れることをよしとし、それに文学(読書)を加え、はたまた外国に興味を持たせ、小学生の頃から英会話を習わせた。
当時としては画期的な教育だったと思う。気付くとこうして海を越えて一族で毎年1回、音楽会が出来るのだから両親に感謝しなくてはならない。
姉妹といってもアメリカ、神奈川、静岡とてんでんバラバラに、それぞれ忙しく活躍する身である。
皆で会うといっても、お正月くらいしかないので春のコンサートを機会にこうして出会えることは幸せなことだと思う。
今回は兄が仕事で日本に来られなかったので、姉が日本歌曲とイタリアオペラを歌い、もう1人の姉が弾き語り(シャンソンとジャズピアノが弾けるのだ)、日本の甥っ子がトランペットを姪っ子がピアノ独奏をした。
また、アメリカの甥がヴァイオリンを、6歳になる姪っ子が日本のおばあちゃんから習った、たどたどしい日本語で「赤い靴」と「青い目の人形」を無伴奏で歌った。これが大変受けた。
だいたい自慢になるが6歳で、伴奏無しで転調した跳躍の音程をはずさず歌うなんざーこの年齢で、とても真似出来ることではないのでびっくり驚きである。
祖父母はクロアチアのチェロの教授だし、両親が音楽家なら当然といえば当然なのだが、血は争えないものだ。
悲しいのが三好家だ。私は忙しくて練習が出来ないので独奏は勘弁してもらい、姪っ子と連弾をさせてもらい、それと甥のアントンのヴァイオリンの伴奏をした。
いとこの中では1人息子だけ出演しなかった。彼は中学までピアノを弾いたが、その後は同じキーボードでもパソコンキーボード専門だから、この音楽会には参加出来ないのである。
こうなったら今後は孫に期待をしたいと思っている。
当日はみぞれ降るほどの花冷えの中で、地元のホールに300人程の観客が詰めかけ、大盛況に終わることが出来た。
「両親が喜んでくれたのが何よりだった」と、姉達と「お互い忙しかったけど親孝行出来てよかったね」と語り合った。
中心になってチケットを売ってくれた地元にいる姉は、おかげで2キログラムもやせたらしい。
姉に感謝したい!! |
|
|
|
| 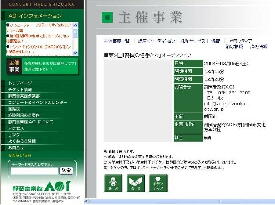 3月6日(土)静岡AOIで「静岡の名手たち」のオーディションがあった。 3月6日(土)静岡AOIで「静岡の名手たち」のオーディションがあった。
このオーディションは、今年で9回目を迎える。静岡在住の音楽家(学生〜一般)を無料で公募し、オーディションが行われ、7月10日のコンサートの出演者を決める。
レベルはかなり高くて「静岡の名手たち」と銘打った通り、静岡のトップレベルの演奏家の音楽会である。
うちの教室からは、国立音大4年のR.M.さんと東京学芸大のM.M.さん姉妹が2台ピアノで出演した。
全く正反対の性格の2人は思春期の頃は、よくぶつかったが、東京で2人で暮らすようになってからは本当に仲が良い。将来、教えることよりも演奏活動を中心に頑張って行きたいと2台ピアノのレパートリーを着実に増やしている。
昨夏ピティナに2台ピアノでコンペに出たが、惜しくも本選優秀賞で全国大会は逃した。
姉妹は息もぴったりと思ったが、敗因は選曲も影響しているのではないかと言われたのを機会に、デュオでは第一線で活躍されているプロの先生に直接教えを乞い、舞台栄えのする選曲をして頂いたのがインファンテのアンダルシア舞曲だ。
スペインの情熱と哀愁ただよう、激しくも切ない、そして華麗な1曲である。この曲を東京で何度かレッスンしたが、教えるだけでも汗をかく程の大曲だ!
この曲でオーディションを受けたのだが、見事アンサンブル部門で通過、7月10日のコンサート出演が決まった。
小さい時、ピアニストを目指してきた2人だが、デュオで演奏活動をしていきたいのが現在の2人の夢である。Primoは情熱的な妹、良く音を聴き、合わせ上手、支え上手のSecondの姉、絶妙のデュオだと思うがまだまだこれから修業だろう。
私としては、これからも2人の夢を支えていってあげたいと思う!! |
|
|
|
| 3月7日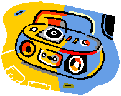
先週、今週末は生徒と、テープ審査提出用のテープを吹き込んだ。
ひとつは夢コン(フリューゲル・ピアノコンチェルト・フェスティバル)用のテープともう1つは他のコンクール用だ。
最近では、申し込み数が多いコンクールの場合、時間や場所の関係上、書類選考やテープ審査を行うことが増えてきた。テープ審査の難しさと注意事項を書きたい。
以前、国際コンクールのテープ審査用に3人の生徒と共に、会場を借り切ってテープを作ったことがある。
その時、3人の内1人は高熱を出していて、何度録音しても失敗ばかりだった。時間切れで、仕方無く、泣く泣く失敗だらけのテープを出す羽目になった。
しかし、残りの2人は絶好調で普段通りの演奏で録音出来た。
数ヵ月後、合否を聞いて驚いた。その失敗だらけのテープの生徒は見事テープ審査を通り、うまく弾けた筈の生徒のうちの1人が落ちていた。
意外な結果に首をかしげた。その子に後で聞くと、ホールでの演奏が今一歩だったうちの1曲を家で取り直し、ホールでの演奏にプラスして、合成して出したらしい。
その時はまだ、私もテープ審査のイロハを知らなかったが、それだけはご法度だった。
何といっても音源は、1つでなくてはいけないのだ。
その理由が今回よく分かった。夢コンはカラオケに合わせ、ピアノのコンチェルトを弾くのだが、このカラオケが曲者なのだ。
バックのカラオケはいつも同じだし、相手の動きを読んでしまえば良いのだと思ったら大違い。微妙に各々の箇所でテンポが変化している。流れを飲み込むといっても、こっちも生身の人間だから、一呼吸遅れたり、一瞬集中力に欠けたりしたら最期、もうずれてしまうのだ。
5分間の曲ともなると、最初はうまくいっても、最後の1音ずれていたらもう一度取り直し。
今度は中間部でずれてもう1回。そのうち疲れて、合うは合うけど、ただの棒弾きの出来上がりだ!
そんなこんなで疲れ果てた。夜も更けて、もう無理と思いつつも、"人間なんでも集中力だ!"と思い直し、"横に立って"「もうしっかり弾かなかったらこれで全ておしまいだからね。」
と脅迫して弾かせたら、なんとその子の力が出せたテープが出来たから驚くではないか。
演奏は常に1回だけ、消しゴムもなければ見直しも出来ない世界だからこそ、その緊張感の中で全てを出しきれるのだと再認識した。演奏とはこの1回だけのありがたさでもある!!
後はアクシデントだ。ホールを借りる場合、良い調子で録音をしていても、ホールの時報のブザーが鳴ったらおしまいだ。
あり得ない機械(MD)の不調、録音が消えトビトビだ。何でこんな時、よりによって機械が壊れるのだ。
大体、テープ審査用のテープ作りなどは、ぎりぎりまで練習して、良いのを出したいから、提出期限間際にホールを借りているので、この日入れないと後は無いのだ。
先生が焦ると生徒も焦ってどんどんテンポが上がり、ミスを呼ぶ。やっと最低ランクぎりぎりで、1曲ずついれてもう1回と弾いていたが、会場に大きく流れた"蛍の光のテーマ"、残酷!!
やっぱり全ては時間に余裕をもって臨むべきだ。
欲を出してはいけないのだ!!時間の余裕。ホールの下見(時報の確認)。機械やテープは少し多めに用意する(アクシデントに備え)。
まあ実力が無いのはカバー出来ないが、せめて無事に提出したいではないか。
それにしてもコンクールは一回だけしか弾けないから意味があるのだとつくづくと思った。
何度も弾けばよくなるというわけでは無い。人間の集中力は短いのだ!!
さて結果、苦労の甲斐あり、夢コンはY.N.さん(小5)、C.U.さん(中1)が無事、審査合格した。 |
|
|
|
| 2月22日、ピティナ大阪検定の審査で大阪に行った。
ピティナの審査をするようになって8年目になるが、検定のみの審査は初めてなので少し緊張した。
しかし大阪では、久しぶりに引っ越した生徒のレッスンも出来るので、その日を心待ちにしていたのに、今回は残念な事に、前日に生徒の母親がインフルエンザにかかり、ピアノのレッスンどころではなくなってしまった。
(しかし、レッスン無しで、TELのみでグレコンを受けた生徒は優秀賞だった!)
仕方なく、早く寝てしまうのも何なので、大阪で"食い倒れ"をしてみたいと大阪に以前住んだことのある知人にメールで誘導してもらい、"ネギ焼き"のおいしいという店を電車を乗り継ぎ行ってみた。
着くとびっくり、20人もの長蛇の列。"行列の出来るラーメン"は都内ではよく見かけるが、「気の短い大阪人が、20人もニコニコ苛々せず待っている店なんてすごい。」と思い、私も最後尾についてみた。
するとどうだろう?すぐ注文を聞きに来たではないか?
1時間待つ覚悟だったのに、20名しか座れないカウンターから首尾よく順繰りに席が開き、30分もしないうちに自分もカウンターに座っていた。
座ったと同時に既に注文済みのネギ焼きがドーンと目の前にある。
せっかくだからデラックス・ネギ焼き(イカ、肉、えび入り)を頼んだのだが焼きたてのネギ焼きに醤油をかけ、しぼりたてのレモン汁をパーッと。「ああ、もうだめこれを書きながら、よだれが………。」
生ビールをお伴にアツアツのネギ焼きを口にほおばったら「幸せ」で、見ず知らずの隣のお客さんに笑いかけてしまう始末だ。人も食べ物もおいしい大阪が好きだったが、またまたファンになってしまった。
また、ネギ焼きを食べたーーい!
翌日は100名程の検定審査だった。検定といえど、レベルの高いこと、高いこと。
それも年齢が低い程レベルが高いのだ。コンペも年々レベルの上がるいっぽうで、ステップも同様だし、検定もしかりだから、日本の音楽教育の水準の向上にはびっくりする。
よい生徒を育てる=指導者を育て地域と中央の格差をなくすという、故福田靖子先生の願いがしっかりと浸透しているのを感じた。
コンペに出る生徒をたくさん抱える指導者としては、ますます厳しい世の中である。
審査では、また同年齢の先生方と交流があった。こうして日本中に仕事を通して友人が出来るのが何より嬉しい。有意義な一日を送った。 |
|
|